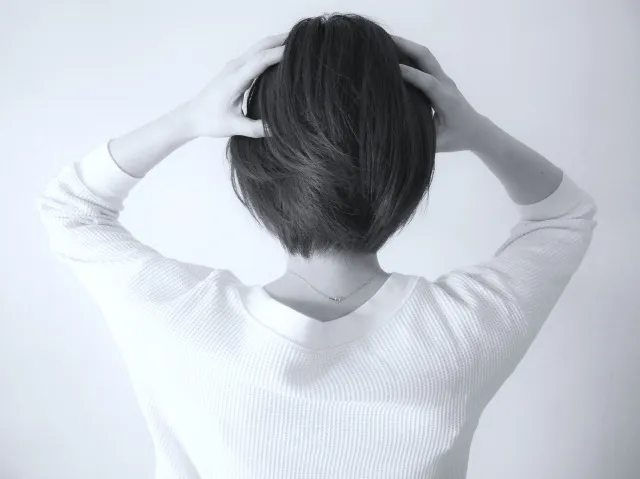双極性障害と不安障害の併存と生活の質を向上させるためのヒントについて
2024/12/05
みなさん、こんにちは。
神戸市や芦屋市、西宮市などの近隣都市で活動しているこころのケア心理カウンセリングルームの心理カウンセラー(公認心理師) 駒居義基です。
さて、双極性障害を抱えている方の中には、症状の管理に難しさを感じる方も少なくありません。
その背景には、不安障害の併存が関係している場合があります。
今回は、「Anxiety Disorder Comorbidity in Bipolar Disorder Patients」という研究を基に、双極性障害と不安障害の関連性について詳しく解説します。
この内容を通じて、併存する症状への理解を深め、効果的なケアや治療のヒントを得ていただけたらと思います。
双極性障害とは?
双極性障害とは、気分が極端に高揚する「躁状態」と、深い落ち込みを感じる「抑うつ状態」を繰り返す精神疾患です。
これらの状態は、単なる気分の浮き沈みとは異なり、日常生活や人間関係、仕事などに大きな影響を及ぼすことがあります。
躁状態では、異常に活動的でエネルギッシュになる一方、現実的でない計画を立てたり、衝動的な行動を取ることがあります。
一方、抑うつ状態では、意欲の低下や興味の喪失、無価値感を強く感じ、時には抑うつ状態が非常に深刻なることもあります。
この疾患は、脳内の神経伝達物質のバランスの乱れや、遺伝的要因、ストレスなどが発症の要因とされています。
また、双極性障害は一つの疾患ではなく、「双極Ⅰ型」と「双極Ⅱ型」という2つの主なタイプに分かれます。
双極Ⅰ型では、激しい躁状態が現れるのに対し、双極Ⅱ型では軽躁状態と呼ばれるやや穏やかな高揚状態と抑うつが繰り返されます。
治療には、薬物療法(気分安定薬や抗うつ薬)、心理療法(認知行動療法など)が組み合わされることが一般的です。
適切な治療を受けることで、症状をコントロールし、安定した日常生活を送ることが可能です。
また、家族や周囲のサポート、セルフケアも重要な役割を果たします。双極性障害は長期的な管理が必要な疾患ですが、早期に診断し、適切な治療を受けることで、より良い生活を築くことができます。
不安障害とは?
不安障害とは、過剰な不安や恐怖を感じる状態が持続し、日常生活に支障をきたす精神疾患の総称です。
私たちが日常的に感じる不安や心配は、ある程度は自然な反応であり、危険を回避するための役割を果たします。
しかし、不安障害の場合、その不安が現実的な危険や状況を超えて過剰になり、本人がコントロールできなくなることが特徴です。
不安障害にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。
例えば、理由のない激しい不安発作が突然起こる「パニック障害」、日常的な出来事や未来への過度な心配が続く「全般性不安障害」、社会的な場面での緊張や恥をかくことへの強い不安を伴う「社交不安障害」などがあります。
これらの障害は、心拍数の増加、息苦しさ、発汗、震えといった身体的な症状と、集中力の低下、イライラ感、悪い結果を繰り返し考える反すう思考などの心理的な症状を引き起こします。
こうした症状は、仕事や学校生活、人間関係に深刻な影響を及ぼし、場合によっては孤立やうつ状態を招くこともあります。
不安障害の原因は、脳内の神経伝達物質のバランスの乱れ、遺伝的要因、ストレス、過去のトラウマなど、多岐にわたります。
治療には、薬物療法(抗不安薬や抗うつ薬)、心理療法(認知行動療法など)、そしてリラクゼーション法や運動といったセルフケアが用いられます。
この精神疾患も適切な治療を受けることで、症状を管理し、不安と向き合いながら日常生活を取り戻すことが可能です。
双極性障害における不安障害の影響
双極性障害を抱える方の中には、不安障害を併発するケースが非常に多いことが分かっています。
この併存は、双極性障害の症状や治療にさまざまな影響を与えます。
まず、不安障害を併発している場合、双極性障害の発症年齢が早くなる傾向があります。
これは、症状が複雑化しやすく、治療が必要となる時期が早まることを意味します。
また、不安障害を併存する方は、躁状態と抑うつ状態のエピソードがより頻繁に起こりやすく、これにより症状が重症化する傾向があります。
特に抑うつエピソードでは、不安障害が併存しているとその期間が長引きやすいことが知られています。
これにより、日常生活や仕事、対人関係への影響が大きくなり、生活の質(QOL)が低下することがあります。
さらに、不安障害があると治療への反応が悪くなる可能性があります。
例えば、双極性障害の治療で用いられる薬物療法が十分に効果を発揮しない場合があったり、治療を継続する意欲が低下したりすることがあります。
これにより、治療の成功率が下がり、再発のリスクが高まる可能性も指摘されています。
不安障害は、社会的機能にも大きな影響を及ぼします。
人前に出ることや対人関係に不安を感じやすくなるため、孤立しやすく、仕事や家庭生活にも支障をきたすことがあります。
このように、双極性障害と不安障害が併存する場合、症状がより複雑化し、治療が難しくなる可能性があります。
そのため、不安障害の早期診断と適切な治療が、双極性障害の全体的な症状管理と生活の質の向上において重要な鍵となります。
不安障害を考慮した双極性障害のケア
1. 不安障害を早期に診断する
双極性障害の治療を進める上で、不安障害の併存を早い段階で見つけることが重要です。
医療機関での診察時に、不安に関する症状を具体的に伝えることで、適切な診断が下されます。
不安症状が見逃されると、双極性障害の治療が不十分になりがちです。
2. 複合的な治療計画を立てる
不安障害を併存している場合、治療には双極性障害だけでなく、不安障害にも対応できる方法を組み込む必要があります。
1:薬物療法
気分安定薬や抗うつ薬に加え、不安症状を軽減するために、抗不安薬が使用されることがあります。
ただし、薬物療法の内容については、しっかりと医師とよく相談しましょう。
2:心理療法
認知行動療法(CBT)は、不安障害の症状を緩和し、双極性障害の感情コントロールを助ける効果があります。
3. ストレス管理を取り入れる
不安はしばしばストレスと結びついています。以下のような方法を取り入れることで、ストレスを軽減し、不安症状の悪化を防ぐことができます。
1:マインドフルネスや瞑想
現在の瞬間に意識を集中させることで、不安を軽減します。
2:運動
ウォーキングやヨガなどの適度な運動は、ストレスを和らげると同時に、気分を安定させる効果があります。
4. 生活習慣の整備
不安や双極性障害の症状は、生活リズムの乱れによって悪化することがあります。
規則正しい生活を送ることで、症状を安定させることが期待できます。
1:睡眠の確保
十分な睡眠を取ることが、症状の安定に直結します。
2:健康的な食生活
栄養バランスの取れた食事が、心身の健康を支えます。
3:カフェインやアルコールの制限
これらは不安を悪化させる可能性があるため、控えることが推奨されます。
5. サポートネットワークを活用する
周囲からの支援は、治療の成功に大きな役割を果たします。
1:家族や友人に状況を共有する
症状について話し、サポートをお願いすることで孤立を防げます。
2:カウンセリングの活用
専門のカウンセラーと話すことで、孤独感が軽減されるだけでなく、回復へのプロセスを進めることができます。
6. 再発防止のためのフォローアップを続ける
不安障害と双極性障害は再発しやすい疾患です。
定期的に医師やカウンセラーと面談し、症状の変化を確認することが重要です。
小さな変化にも気付き、早めに対処することで、症状の悪化を防ぐことができます。
7. 自分自身を受け入れる
不安障害や双極性障害を抱えていることに罪悪感を持たず、「自分に合ったケアを探している途中」と前向きに考えることが大切です。
完璧を目指さず、少しずつ良い方向に進んでいる自分を認めてください。
不安障害を考慮したケアは、双極性障害を抱える方の回復を大きくサポートします。
適切な診断、治療、日常生活の改善を組み合わせて、健康的な生活を目指しましょう。
包括的なアプローチで症状改善を目指す
双極性障害と不安障害を併存している方にとって、症状を管理し、より良い生活を築くためには、包括的なアプローチが欠かせません。
この2つの疾患は、それぞれ独立した特徴を持ちながらも互いに影響し合うことが多いため、一面的な治療では不十分な場合があります。
しかし、適切な診断と治療を受け、生活習慣や自己ケアに工夫を凝らすことで、症状の改善が期待できるのです。
不安障害が併存していることで、双極性障害の症状がより複雑に感じられることもあるでしょう。
「自分はどうしてこうなってしまったのだろう」「何を試しても改善しないのでは」といった不安や落胆を抱える瞬間もあるかもしれません。
それでも、現代の医療や心理学は、これらの複雑な症状に対応するための効果的な治療法を提供しています。
認知行動療法(CBT)や薬物療法を活用し、専門家のサポートを受けながら、自分に合った治療プランを一緒に作り上げていくことができます。
また、治療の一環として、日常生活における小さな変化が大きな成果を生むこともあります。
十分な睡眠を取る、バランスの良い食事を心掛ける、そしてストレスを感じたときに自分を責めるのではなく、「ここからどう進むか」を考える姿勢を持つことが重要です。
こうしたセルフケアは、一見すると簡単なように思えるかもしれませんが、実際には回復への重要な一歩となります。
さらに、周囲からのサポートも回復を促進する大きな要因です。家族や友人に状況を理解してもらい、共に歩んでくれる存在がいることは、孤独感を軽減し、希望を抱き続ける力になります。
また、カウンセリングを通じて、「自分だけではない」という安心感を得られるでしょう。
「全てを完璧に解決しなければならない」と思う必要はありません。
双極性障害や不安障害は、それぞれの人生の中で向き合うべき一部分に過ぎません。
日々の中で小さな前進を重ねていくことが、最終的には大きな変化につながります。
少しずつ自分自身を受け入れ、自分のペースで回復の道を歩んでいきましょう。
どんな困難な状況にあっても、回復の可能性は常に存在します。
そして、その道のりを一緒に歩むために、私たちカウンセラーは全力でサポートします。
一人ではありません。あなたには、歩んでいける力が必ずあります。
包括的なアプローチで、より良い明日を目指して一緒に進んでいきましょう。」
参考論文
----------------------------------------------------------------------
こころのケア心理カウンセリングRoom
兵庫県芦屋市浜芦屋町1-27 サニーコート浜芦屋302号
電話番号 : 090-5978-1871
----------------------------------------------------------------------
この記事の執筆者
駒居 義基(こころのケア心理カウンセリングルーム 代表)
心理カウンセラー(公認心理師)。20年以上の臨床経験と心理療法の専門性を活用して、神戸市や芦屋市、西宮市の近隣都の方々にお住いの心のお悩みを抱えている方に対して、芦屋市を拠点に最適なサポートを提供しています。
プロフィールはこちら