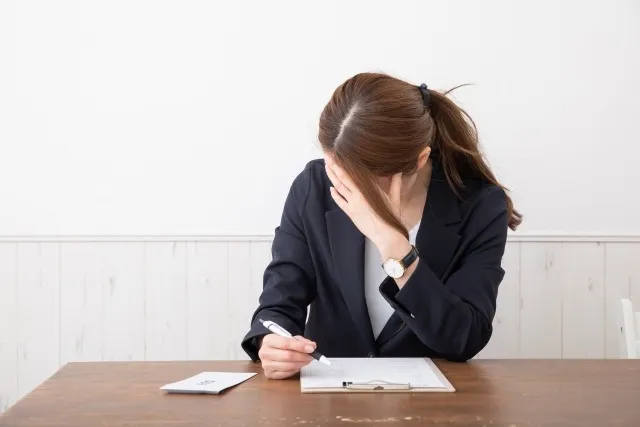双極性障害の経過を左右する「抑うつ症状」とは?
2025/02/06
みなさん、こんにちは。
神戸市や芦屋市、西宮市などの近隣都市で活動しているこころのケア心理カウンセリングルームの心理カウンセラー(公認心理師) 駒居義基です。
さて、双極性障害というと「躁状態」の激しい変化が目立つため、「活動的になりすぎる病気」と認識されることが少なくありません。
しかし、実際には、双極性障害の多くの方が「抑うつエピソード」の期間の方が長く、苦しむ時間が多いことが研究によって示されています。
そのため、このブログでは双極性障害における抑うつエピソードの特徴やその影響、そして適切な対処法について詳しく解説します。
1. 双極性障害における抑うつ症状の特徴
双極性障害には双極性I型と双極性II型の2つの主要なタイプがあります。
双極性I型
→明確な躁状態(ハイテンション、睡眠不足でも活動できる、衝動的な行動など)が見られる一方で、抑うつ状態も経験する。
双極性II型
→軽躁(躁の症状が比較的軽い)が特徴で、抑うつエピソードが主に現れる。
● 抑うつエピソードの特徴
抑うつエピソードの症状は、典型的なうつ病の症状と似ていますが、双極性障害では以下のような特徴が見られます。
・通常のうつ病よりも変動が大きい(気分が良い日があっても、翌日には再び落ち込むことが多い)
・ 反応性のうつ(環境によって気分が持ち上がることがあるが、またすぐに落ち込む)
・自責感が強い(特に「以前の躁状態で迷惑をかけた」という思いが強くなることがある)
・睡眠の問題(過眠・不眠が交互に現れることがある)
・エネルギーの波(疲労感が強い日と比較的元気な日が交互に訪れる)
2. 「双極性障害では抑うつエピソードが長く続く」という研究結果
1.主な研究結果
● 双極性障害では、躁状態よりも抑うつエピソードの方が多くの時間を占める
双極性障害と聞くと、多くの人は「躁状態」の激しい気分の高まりやエネルギッシュな行動をイメージしがちです。
しかし、この研究では、実際の病歴において双極性障害のエピソードの60~70%が抑うつ症状で占められていることが明らかになっています。
この割合は、双極性障害の方が躁状態よりも圧倒的に長い期間、抑うつの苦しみに直面していることを意味します。
多くの双極性障害を抱える方にとって、躁状態は比較的短期間であり、日常生活に影響を与えるのはむしろ長期的な抑うつ症状の方なのです。
また、抑うつエピソードの持続期間が長いほど、再発リスクが高まることも示唆されており、適切な治療と継続的なサポートの重要性が浮き彫りになりました。
● 特に双極性II型では抑うつエピソードの割合が圧倒的に高い
先述しましたように、双極性障害には主に以下の2つのタイプがあります。
双極性I型
→明確な躁状態(極端なハイテンション、過活動、睡眠不足でも元気など)がみられるが、抑うつエピソードも経験する。
双極性II型
→躁状態(軽躁)はI型よりも軽いが、抑うつエピソードがより長く、重く続く。
研究によると、双極性II型の方は、病歴の大部分を抑うつ状態で過ごすことが明らかになりました。軽躁の期間は短く、抑うつエピソードの長さや頻度が際立っています。
この結果は、双極性II型の方にとって、うつ病と似た症状を経験する期間が長く、生活の質が低下しやすいことを示唆しています。
軽躁の時期があるため、一般的なうつ病と区別されますが、日常生活への影響は深刻であり、適切な診断と治療が不可欠です。
● 抑うつエピソードの期間が長いほど、再発リスクが高まる
本研究では、抑うつ症状の持続期間が長いほど、双極性障害の再発リスクが高まることも指摘されています。
・抑うつエピソードが長期間続くことで、社会的な孤立が進み、日常生活の回復が難しくなる。
・仕事や人間関係の維持が困難になり、ストレスの増加によって再発のリスクがさらに高まる。
・薬物療法の中断や不適切な治療が抑うつ状態を悪化させることもある。
つまり、早期に適切な治療を受け、抑うつエピソードを短縮することが、双極性障害の長期的な管理にとって極めて重要であると言えます。
2.研究結果の臨床的意義
この研究の結果を踏まえると、双極性障害の治療において、以下の点が特に重要になります。
● 抑うつエピソードに焦点を当てた治療が必要
双極性障害の方において、抑うつ期間が長いため、気分安定薬や認知行動療法(CBT)などを活用した継続的な治療が不可欠です。
● 双極性II型は特に抑うつ症状への対策が求められる
・軽躁エピソードよりも、長期化しやすい抑うつ症状の管理が重要。
・一般的なうつ病と異なり、気分の波を考慮した治療計画が求められる。
● 早期の介入が再発リスクを軽減する
・抑うつエピソードが長引くほど再発リスクが高まるため、適切な治療介入を早めに行うことが再発予防につながる。
3.まとめ
この研究は、双極性障害において抑うつエピソードが長く続くことが最も大きな課題であることを明確に示しました。
特に、双極性II型の方では抑うつエピソードの割合が高く、日常生活への影響が大きいため、適切な治療とサポートが不可欠です。
✔ 60~70%の時間が抑うつ症状で占められる
✔ 双極性II型は特に抑うつ期間が長い
✔ 早期治療が再発リスクを軽減する
この研究結果を踏まえ、躁状態だけでなく、抑うつ症状に焦点を当てたケアが双極性障害の治療において最も重要であるという視点が、今後の臨床実践において求められています。
3. 抑うつ症状への適切な対処法
双極性障害において、抑うつエピソードは最も長く続きやすい症状であり、日常生活に深刻な影響を及ぼします。
そのため、適切な対処法を理解し、できるだけ早期に実践することが重要です。
ここでは、具体的な治療法や生活習慣の改善策、社会的なサポートの活用方法について詳しく解説します。
3-1. 早期の治療介入が重要
抑うつ症状が続くと、生活の質が大きく低下し、社会的な孤立を引き起こしやすくなるため、できるだけ早く専門的な治療を受けることが重要です。
特に、双極性障害における抑うつエピソードは放置すると慢性化しやすく、再発リスクも高まるため、適切な医療介入が必要となります。
● 薬物療法:気分の安定を促し、抑うつ期間を短縮
薬物療法は、双極性障害において気分の波をコントロールするための基本的な治療法です。
特に抑うつエピソードが長引く場合、薬物療法が有効な場合が多くあります。
● 心理療法:認知のバランスを整え、抑うつに対処
心理療法は、抑うつの悪循環を断ち切るための重要な手段です。
特に、認知行動療法(CBT)は、双極性障害の抑うつエピソードに有効であることが研究で示されています。
ネガティブ思考を客観的に見直す
→うつ状態では「自分はダメだ」「何をしても無意味」といった思考に囚われがちですが認知行動療法ではこうした思考の偏りを修正する。
行動の活性化
→抑うつ状態では活動レベルが低下するため、小さな目標を設定し、少しずつ行動を増やすことで回復を促す。
心理療法は、薬物療法と併用することでより効果的であるため、主治医やカウンセラーと相談しながら取り入れることが推奨されます。
3-2. 生活習慣の見直し
抑うつエピソードが続くと、日常生活のリズムが乱れやすく、心身の負担がさらに増大します。
しかし、生活習慣を見直すことで、抑うつ症状を軽減し、回復を早めることができると考えられています。
以下の点に注意しながら、少しずつ日常生活を整えていきましょう。
● 規則正しい生活リズムを維持する
特に睡眠時間の確保が重要。双極性障害では、睡眠リズムが乱れると症状が悪化しやすいため、毎日同じ時間に寝起きする習慣をつける。
また、朝の光を浴びることで体内時計を整え、抑うつ症状を軽減する効果が期待できます。
● 適度な運動を取り入れる
運動は、脳内のエンドルフィン(幸福ホルモン)を増やし、気分を安定させる効果があります。
ウォーキングやストレッチ、軽いヨガなど、無理のない範囲で行うことが重要です。
屋外での運動は特に効果的で、日光を浴びることでビタミンDの生成が促進され、気分が向上します。
● 食事のバランスを整える
栄養不足は気分の乱れを引き起こす要因となるため、バランスの取れた食事を意識しましょう。
またカフェインやアルコールの過剰摂取を控えることで、神経の安定を保つことができます。
3-3. 社会的なサポートを活用する
抑うつ症状が続くと、人との関わりを避けたくなることが多くなりますが、適切な社会的サポートは回復にとって不可欠です。
孤立してしまうと、抑うつ症状がさらに悪化しやすくなるため、信頼できる人とのつながりを持つことを意識しましょう。
● 家族や友人にサポートを求める
・自分の状態を素直に話すことで、精神的な負担を軽減する。
・一緒に過ごす時間を増やすことで、気分が安定しやすくなる。
● カウンセリングを利用する
専門家と話すことで、客観的な視点から自分の状態を理解し、適切なアドバイスを得ることができます。
また認知行動療法(CBT)を取り入れたカウンセリングは、双極性障害における抑うつ症状の軽減に効果的です。
まとめ
双極性障害の抑うつエピソードは、長期化しやすく、日常生活に大きな影響を与えます。
そのため、早期の治療介入・生活習慣の見直し・社会的サポートの活用が重要です。
✔ 早期の治療介入:薬物療法+心理療法(CBT)で症状の管理を行う
✔ 生活習慣の見直し:睡眠・運動・食事のバランスを整える
✔ 社会的なサポートを活用:家族・友人・専門家の力を借りる
双極性障害の抑うつ症状は、適切なケアを受けることで軽減し、日常生活を快適に過ごすことが可能になります。焦らず、自分に合った方法を見つけて、適切なケアを行ってまいりましょう。
参考論文
Depressive Episodes and Symptoms Dominate the Longitudinal Course of Bipolar Disorder)
----------------------------------------------------------------------
こころのケア心理カウンセリングRoom
兵庫県芦屋市浜芦屋町1-27 サニーコート浜芦屋302号
電話番号 : 090-5978-1871
----------------------------------------------------------------------
この記事の執筆者
駒居 義基(こころのケア心理カウンセリングルーム 代表)
心理カウンセラー(公認心理師)。20年以上の臨床経験と心理療法の専門性を活用して、神戸市や芦屋市、西宮市の近隣都の方々にお住いの心のお悩みを抱えている方に対して、芦屋市を拠点に最適なサポートを提供しています。
プロフィールはこちら