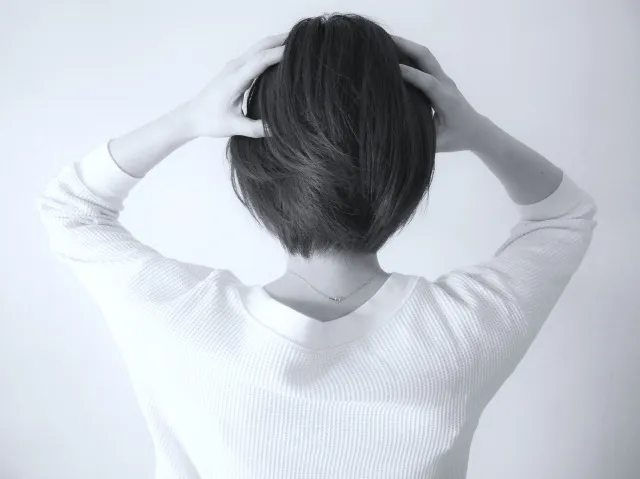なぜ「自己受容」が人付き合いを楽にするのか
2025/03/15
みなさん、こんにちは。
神戸市や芦屋市、西宮市などの近隣都市で活動しているこころのケア心理カウンセリングルームの心理カウンセラー(公認心理師) 駒居義基です。
今日は自己受容が進むと他者との関係が良好になるメカニズムについてお伝えいたします。
自分の苦手な部分を認められずにいると、無意識のうちに他人にも同じ厳しさを向けてしまいがちです。
たとえば、自分の短所を見たくない気持ちが強いほど、相手の欠点が気になってしまいます。
一方、自分が「いまの自分も含めて受け止めよう」と思えたなら、他人についても「相手には相手のままでいい部分がある」と考えやすくなります。
つまり自己受容の視点を育むほど、周囲の人を自然と受け入れる度合いも高まり、人間関係を円滑にしてくれるのです。
1.「自己受容」と「自己肯定」の違い
1-1.すべてを「素晴らしい」と思う必要はない
一般的に「自分を受け入れる」と聞くと、「自分を好きになる」あるいは「自分の長所を伸ばしてポジティブに認める」といったイメージを持ちやすいかもしれません。
しかし、本来の自己受容は「すべてをいいと思わなければいけない」ということではありません。
たとえば、内気な性格や短気なところなど、自分のなかに「これは嫌だな」と感じる面がある場合、それを無理に「素晴らしい」と言い換えようとしなくても大丈夫です。
重要なのは「嫌だな」と思う部分も、今の自分を構成する要素の一つとして「そういう部分もあるのだ」と受け止めることです。
1-2.自己肯定は条件付き、自己受容は無条件
自己肯定感を高めようとするとき、つい「できるから好き」「優れているから大丈夫」といった条件付きの考えになりがちです。
このような条件付きの好き嫌いは、思うように成果が出なかったり失敗したりしたときに「自分の価値が下がった」と感じやすいリスクも抱えています。
一方、自己受容では「得意なところも苦手なところも含めて自分」であると受け止める姿勢が基本です。
たとえば、「内気な自分をなんとか直そう」と必死になったり、「内気でもポジティブな面がある」と無理に思い込もうとしたりするのではなく、「内気なところもあれば、明るい部分もある。それらをひっくるめて自分という存在なんだ」と認める感覚です。
こうして「良い・悪い」という評価を一旦横に置き、「今の自分はこうなんだな」という理解と許しの姿勢を持てば、不思議と心が軽くなり、自分を追い詰めずにいられるようになります。
2.自己受容は変化のスタートラインになる
私たちが「太ってしまった」「食べ過ぎをやめたい」など、具体的な行動を改めたいと考えるとき、まず取りがちなのが「自己批判」です。
たとえば「こんなに食べてしまう自分はダメだ」と自分を責めてしまうパターン。
しかし、このアプローチはストレスをさらに増幅させるだけで、かえって行動をコントロールしにくくなることが多いのです。
2-1.行動を変える鍵は「今の自分を知る」こと
自己批判を続けると「どうして自分はいつもこうなんだ」と意気消沈し、モチベーションも下がってしまいます。
そこで大切なのが、まずは「今の自分」を客観的に受け止める姿勢です。
● なぜ、その行動をしてしまうのかを知る
たとえば、特定の曜日にだけ食べ過ぎているなら、どんな気持ちがその背後にあるのか、どんな環境がそうさせるのか、ゆっくりと振り返ってみましょう。
● 気づきを得ることで対策が見えてくる
自分の行動を「良い/悪い」とジャッジするのではなく、「今週はどんな場面で、どんな感情のときに食欲が爆発したのか」を探ります。
もし、「上司と長く話した日の夜だけ大量に食べている」ことに気づいたら、対策として「上司との接触後は、いきなり食事をとらず、少し散歩してクールダウンする」などの工夫ができます。
2-2.自分を責めずに興味を持つほうが行動を変えやすい理由
「失敗する自分」ばかりを責めたくなる気持ちは、誰しも少なからず持っているかもしれません。
しかし、自己批判から入ると、ネガティブな感情にとらわれて冷静な判断がしにくくなります。
一方、自己受容のスタンスを持つと「なぜ自分はその行動をしてしまうのだろう」と、やや俯瞰した視点で観察できるようになるのです。
● 長続きする変化
行動の「原因やきっかけ」を突き止めれば、同じシチュエーションを繰り返さないようにする具体策を立てやすくなります。
結果的に、無理やり戒律を課すよりも、継続可能な対策が見つかりやすいのです。
● 行動だけでなく、思考パターンも変わる
自分を責め続けると「どうせ自分はダメだから」と開き直りに陥りやすいですが、自己受容を土台にすると「もう少し別の対処法を試してみよう」という前向きな姿勢が生まれやすくなります。
3.毎日の「自己受容」トレーニング法
3-1.「湧いてきた感情」をそのまま認める
自己受容の入り口としておすすめなのが、「今、自分はこんな感情を抱いている」と声に出してみる方法です。
たとえば、悲しさを感じたら「悲しいんだね」、怒りを感じたら「怒っているんだね」と、シンプルに自分に語りかけてみてください。
3-2.感情を追い払わないことが大事
多くの人は、ネガティブな感情を「良くないもの」として排除しようとしがちです。
しかしそれを抑え込もうとすると、感情はかえって心の奥で暴れ続けてしまいます。
そこで、「悲しみを抱えている自分」を外から眺めるイメージを作るのです。
冷静な第三者の視点で「悲しいんだね」と言ってあげるだけでも、意外と感情が整理されていくものです。
4.自分を受け入れることが、他人を変える第一歩になる
人間関係を良好にするうえで、自分を認める「自己受容」の習慣は大きな力を発揮します。
自分の感情をうまく扱えるようになると、自然と周囲の人への見方や接し方にも変化が生まれるからです。
4-1.自分の感情を落ち着かせやすくなる
自己受容を習慣化していると、イライラや落ち込みといったネガティブな感情が湧いてきたときでも、「いま自分はこういう気持ちだな」と冷静に受け止められるようになります。
極端な自己批判や、逆に感情を否定することが減るため、心のバランスを取り戻しやすくなるのです。
4-2.他人の弱点やミスに寛容になれる
自分の失敗や短所を「まぁ、それも自分だし」と受け入れられる感覚が育つと、相手がミスをしたり、至らない点を見せたりしても「誰しもそういう部分はあるよね」と落ち着いて受け止められます。
ついイライラしてしまう場面でも、「そんなこともあるか」と思えるようになり、人との衝突や摩擦が少なくなるでしょう。
4-3.自分を責める癖が減り、結果的に周囲との関係も緩和される
自分を責め続けると、知らず知らずのうちに他人にも厳しく当たってしまいがちです。
しかし自己受容を続けていると、「自分がこんな気分になるのも仕方ない」とやわらかく受け止められるようになり、そのまま周囲へ向かっていたストレスや攻撃性が減少します。
その結果、周囲の人たちにも優しく接することができ、関係がスムーズに進みやすくなります。
4-4.小さな変化がより大きな人間関係の改善を呼ぶ
「相手のミスを責め立てずにいられる」「自分の機嫌をうまくコントロールできる」といった些細な変化が積み重なることで、周囲の人とのコミュニケーションは格段に向上します。
あまり意識せずとも、笑顔が増えたり、会話がスムーズになったりして、結果として自分自身も生きやすさを実感しやすくなるのです。
このように、自己受容の習慣を続けると、他人を無理に変えようとしなくても、自分の見方や態度が変わることで人間関係全体の質が向上していきます。
小さな行動や考え方のシフトが、大きな変化を生むことをぜひ体感してみてください。
まとめ
無理に「自分の嫌いな面も好きにならなきゃ」と考えなくても、自分の感情や行動の理由を「あるがまま受け止める」ことが「自己受容」の核心。
地道に取り組むことで、自分に対する目線も、他人との関係性も驚くほど変わる可能性があります。
自分を肯定するのが苦手だな、と感じるときこそ「受け入れるだけでいい」と意識してみてください。
時間はかかっても、確実に生きやすさとコミュニケーションの質が変わってくることでしょう。
----------------------------------------------------------------------
こころのケア心理カウンセリングRoom
兵庫県芦屋市浜芦屋町1-27 サニーコート浜芦屋302号
電話番号 : 090-5978-1871
兵庫で人間関係の不安を緩和
----------------------------------------------------------------------
この記事の執筆者
駒居 義基(こころのケア心理カウンセリングルーム 代表)
心理カウンセラー(公認心理師)。20年以上の臨床経験と心理療法の専門性を活用して、神戸市や芦屋市、西宮市の近隣都の方々にお住いの心のお悩みを抱えている方に対して、芦屋市を拠点に最適なサポートを提供しています。
プロフィールはこちら