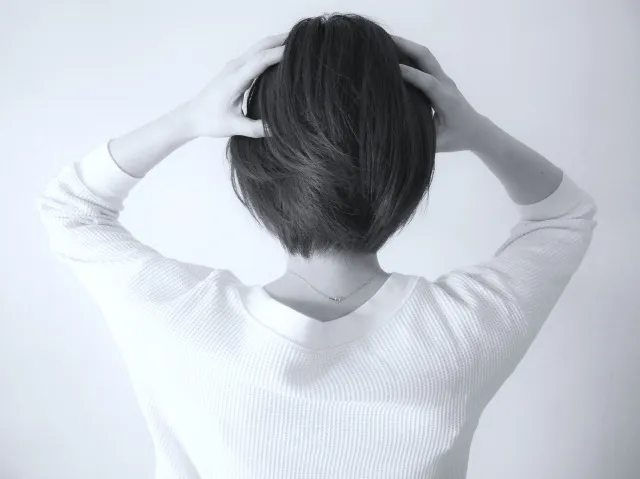なぜ不安は消えない? 不安障害が持続する6つの理由とその克服法
2025/03/18
みなさん、こんにちは。
神戸市や芦屋市、西宮市などの近隣都市で活動しているこころのケア心理カウンセリングルームの心理カウンセラー(公認心理師) 駒居義基です。
さて、不安障害に悩んでいる方の多くは…
「自分の不安がなかなか消えない」
「怖いと思っていることが実際には起こらないのに、不安が続くのはなぜ?」
…と感じられるケースが多々あります。
そして不安障害の方は「不安は『考えても仕方がない』と頭では分かっていても消えない」という方も多くみられます。
そこで、このブログでは「不安障害がなぜ持続するのか」 というテーマについて、Clark(1999)の研究 をもとに詳しく解説し、認知療法の視点からの対処法をご紹介します。
不安障害が持続する6つの心理メカニズム~不安を手放すための理解と対策~
不安障害は「単に不安を感じること」ではなく、不安を維持し、強化する特定の思考や行動パターンによって長引くことが分かっています。
Clark(1999)の研究では、不安障害が持続する理由として、6つの心理的メカニズムが指摘されています。
以下では、それぞれのメカニズムと、それを軽減するための対処法を詳しく解説します。
1.安全確保行動:「やらないと危険?」という誤った関連付け
不安を抱える方は、不安を感じたときに「自分を守るための行動(安全確保行動)」をとることで、不安をコントロールしようとします。
例えば…
✔パニック障害の方が「心臓発作かもしれない」と感じたとき、すぐに座る、深呼吸をする、救急車を呼ぶ。
✔社会不安障害の方が、人と話すのが怖いと感じたときに、人混みを避けたり、視線を下げたりする。
こうした行動は短期的には安心感をもたらしますが、長期的には「不安が和らいだのは、この行動のおかげだ」と思い込んでしまい、本当は危険ではなかったことを確認できないという悪循環を生みます。
● 対処法
少しずつ安全確保行動を減らし、「不安があっても大丈夫」「実際には何も起こらない」ことを体験する機会を増やすことが重要です。
2.注意の偏り:「危険な情報ばかりに目が向く」
不安を抱える方は、無意識のうちに危険な情報に注意を向ける傾向があります。
例えば…
✔社会不安障害の方は、「他人が自分をどう思っているか」を過度に気にし、会話中の相手の些細な表情の変化を「嫌われているサイン」と誤解してしまう。
✔高所恐怖症の方が、高い場所にいるときに「安全な部分」ではなく「落ちるかもしれない部分」ばかりに目がいく。
このように、「危険な可能性」を過大評価し、それにばかり注意が向くことで、不安が強化されるのです。
● 対処法
意識的にポジティブな情報にも目を向けるようにし、「本当に自分が考えているような危険なのか?」とバランスよく状況を評価することが有効です。
3.自動的なネガティブなイメージ:「頭の中で最悪のシナリオが流れる」
強い不安を感じると、最悪の事態をリアルな映像のように思い浮かべてしまうことがあります。
例えば…
✔社交不安の方がプレゼンテーションをする際に、「観客全員が呆れた顔をしている」場面を思い浮かべてしまう。
✔高所恐怖症の方が高い場所に立ったとき、「自分が落ちる映像」が頭の中に浮かんでしまう。
このような「自動的なネガティブなイメージ」は、実際には何も起こっていないのに、脳が「本当に起こること」として認識してしまい、不安を増幅させます。
● 対処法
「最悪のシナリオ」ではなく、「実際に起こりうる現実的なシナリオ」を意識的に想像することで、不安のコントロールがしやすくなります。
4.感情推論:不安を感じる=危険に違いない」という思い込み
「私は不安を感じているから、これは危険に違いない」と、感情そのものを事実と誤認する傾向があります。
例えば…
✔パニック障害の方が「心臓がドキドキする=心臓発作だ」と考えてしまう。
✔飛行機恐怖症の方が、機内で不安を感じると「この飛行機は墜落するに違いない」と確信してしまう。
しかし、「不安を感じること」と「実際に危険であること」は全く別です。
● 対処法
「不安を感じること=危険」ではなく、「今は不安を感じているだけで、本当に危険なのかは確認しよう」と冷静に状況を見つめることが大切です。
5.記憶の偏り:「過去の失敗ばかり思い出す」
不安障害の方は、過去のネガティブな記憶を強く思い出しやすく、ポジティブな記憶を忘れがちです。
例えば…
✔「失敗した経験ばかり思い出してしまう」。
✔「過去に褒められたことやうまくいったことを忘れてしまう」。
この記憶の偏りによって、「自分はいつもうまくいかない」「成功することはない」という思考が強化されてしまいます。
● 対処法
日記をつけるなどして、「ポジティブな出来事も意識的に思い出す」習慣をつけることが有効です。
6.脅威の表象:「失敗=人生の終わり」と考えてしまう
不安を抱える人は、「自分にとっての脅威」を過度に強調して考えてしまうことがあります。
例えば…
✔「一度失敗すると人生が終わる」と考えてしまう。
✔「一回のミスで人から嫌われる」と確信してしまう。
この極端な考え方が、不安をさらに大きくします。
● 対処法
「本当にそこまでの脅威なのか?」を客観的に評価することを習慣化することによって、不安を軽減できます。
まとめ:認知の歪み(妥当でない考え・思考)を理解し、ポジティブな思考パターンを育てる
今回の研究では不安障害の方は、ネガティブな情報を優先的に処理し、ポジティブな情報を受け入れにくいという認知の偏りがあることが明らかになりました。
これにより、否定的な自己概念が強化され、さらに抑うつや不安の症状が悪化するという悪循環が生まれます。
しかし、これは考え方のクセに気づき、少しずつ修正していくことで改善することが可能です。
✔ネガティブな思考を客観的に見つめる
✔ポジティブな情報にも目を向ける習慣をつける
✔小さな成功体験を積み重ね、自信を育てる
✔カウンセリングを活用し、認知の歪みを修正する
こうした取り組みは少しずつで大丈夫です。
自分自身の思考のクセを理解し、前向きな視点を育てることで、より心が軽くなる日が増えていきます。
不安を抱えている方の心が、少しでも穏やかに過ごせるよう、一歩ずつ進んでいきましょう。
参考論文
----------------------------------------------------------------------
こころのケア心理カウンセリングRoom
兵庫県芦屋市浜芦屋町1-27 サニーコート浜芦屋302号
電話番号 : 090-5978-1871
----------------------------------------------------------------------
この記事の執筆者
駒居 義基(こころのケア心理カウンセリングルーム 代表)
心理カウンセラー(公認心理師)。20年以上の臨床経験と心理療法の専門性を活用して、神戸市や芦屋市、西宮市の近隣都の方々にお住いの心のお悩みを抱えている方に対して、芦屋市を拠点に最適なサポートを提供しています。
プロフィールはこちら