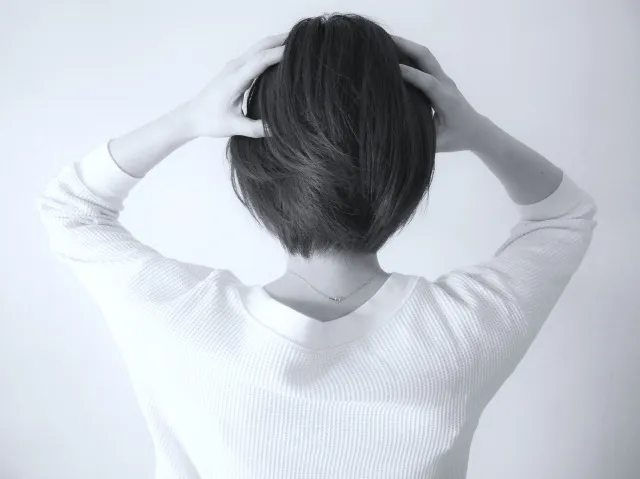強迫性障害から解放されるための第一歩:悪循環を生む「認知モデル」とは?
2025/03/19
みなさん、こんにちは。
神戸市や芦屋市、西宮市などの近隣都市で活動しているこころのケア心理カウンセリングルームの心理カウンセラー(公認心理師) 駒居義基です。
さて、強迫性障害(OCD)は、「不合理で制御が難しい強迫観念」と「それを打ち消そうとする強迫行動」を特徴とする精神疾患です。
例えば、「手が汚れているかもしれない」と感じると、何度も手を洗わずにはいられない、「火の元を確認したか心配になると、繰り返し確認しないと安心できない」といった症状がみられます。
そこで、このブログでは、Salkovskis(1999)の論文を踏まえつつ、強迫性障害の理解を深めるとともに、認知行動療法(CBT)による治療アプローチを解説します。
1.強迫性障害の認知モデル:なぜ強迫行動が生まれるのか?
強迫性障害(OCD)は、単なる「几帳面すぎる性格」や「心配性」といった特徴とは異なり、認知の偏りが引き起こす心理的な悪循環によって維持される精神疾患です。
強迫性障害を持つ方の考え方には共通する特徴があり、それが強迫観念や強迫行動を引き起こしていることが明らかにされています。
そこで以下では、強迫性障害の発症や持続に関わる「責任感の過大評価」と「強迫行動の悪循環」について詳しく解説し、なぜこの病気が長期化しやすいのかを理解していきます。
1-1. 強迫性障害の発症と維持に関わる「責任感の過大評価」
強迫性障害を持つ方の核心的な問題の1つとして「責任感の過大評価」があります。
これは、「自分の行動(あるいは行動しないこと)が、誰かに危害を加える可能性がある」と過剰に考えてしまう傾向を指します。
● 責任感の過大評価が生む思考の例
✔「もし私が手を洗わなかったせいで、家族が病気になったらどうしよう」
✔「もし私が鍵をちゃんとかけなかったせいで、泥棒が入ってきたらどうしよう」
✔「もし私がガスの元栓を閉め忘れて、家が火事になったらどうしよう」
このような思考が浮かぶと、強迫性障害の方は「自分の責任を果たさなければならない」と感じ、それを解消するために強迫行動(手洗いや確認行為など) を繰り返してしまいます。
本来ならば、こうした状況では「大丈夫だろう」と判断することもできますが、強迫性障害の方はその判断を下せず、「最悪の事態を防ぐために行動しなければならない」 という強いプレッシャーを感じてしまいます。
1-2. 「強迫行動」は不安を一時的に軽減するが、長期的には悪化させる
● 強迫行動の悪循環
強迫性障害の方が行う確認行動や回避行動は、最初は不安を和らげる役割を果たします。
しかし、これが繰り返されることで、「この行動をしないと不安が消えない」という誤った学習が強化されてしまいます。
その結果、同じ行動を何度も繰り返す必要が生まれ、強迫性障害の悪循環に陥るのです。
● 悪循環の具体例
例1:手洗い
①「手が汚れているかもしれない」 → 「手を洗えば安心できる」 → 「手を洗う」
②「また汚れている気がする」 → 「もう一度洗わなければ」 → 「再び手を洗う」
③このループが続き、何度も手を洗う習慣が形成される
例2:鍵の確認
①「鍵を閉め忘れたかもしれない」 → 「確認すれば安心できる」 → 「鍵を確認する」
②「本当に閉めたか不安になってきた」 → 「もう一度確認しないと落ち着かない」 → 「再び鍵を確認する」
③このループが続き、外出時に何度も鍵を確認しなければならなくなる
1-3. なぜ強迫行動が長期化し、悪化するのか?
強迫性障害の方が行う強迫行動は、最初は「不安を減らすため」に行われます。
しかし、次第に以下のような問題が生じ、行動の回数が増え、症状が悪化していきます。
①「行動しなければ不安は消えない」という誤った学習
✔手を洗えば不安が消える→何度も洗う
✔鍵を確認すれば安心できる→何度も確認する
✔ルールを守れば大丈夫→ルールを細かく決めすぎてしまう
こうしたパターンが続くと、「行動しないと不安が増す」という思い込みが強化され、行動の回数がどんどん増えてしまうのです。
②「完璧でなければならない」という思考
✔「少しでも汚れが残っていたらダメ」
✔「鍵をちゃんと閉めたと100%確信できるまで確認しないといけない」
✔「絶対にミスをしてはいけない」
このように、「100%完璧でなければならない」という思考が、強迫行動を助長します。
③「安心感が持続しない」という問題
✔強迫行動による安心感は、一時的なものにすぎない
✔すぐに新しい不安が生まれるため、また同じ行動を繰り返すことになる
つまり、強迫行動をすればするほど、「行動しないと不安が解消されない」というループが形成されるのです。
1-4. まとめ:強迫行動の悪循環を断ち切るために
強迫性障害の発症や維持には「認知と行動の悪循環」 が深く関わっていることが示されています。
そのため…
✔「責任の重さ」を客観的に見直すことが重要
✔「最悪の事態は本当に起こるのか?」を現実的に考える
✔「完璧を求めすぎず、適度な基準を設定する」
✔「行動せずに不安が自然に減ることを体験する(曝露反応妨害法)」
強迫性障害の悪循環を断ち切るには、「考え方のクセ」を修正し、「不安を行動で解消しない」という経験を積み重ねることが大切です。
もし「強迫行動がやめられない」「不安で日常生活に支障が出ている」と感じたら、一人で抱え込まずに医療サービスやカウンセリングのサポートを受けることをおすすめします。
心が少しでも軽くなるよう、一歩ずつ取り組んでいきましょう。
2.強迫性障害の治療アプローチ:認知行動療法(CBT)
Salkovskis(1999)の研究では、CBTが強迫性障害治療において非常に有効であることが示されています。
特に、「認知の修正」と「行動の変容」の2つのアプローチが重要とされています。
2-1. 認知の修正(考え方を変える)
強迫性障害の方は、「自分が責任を取らなければならない」「何か悪いことが起こるかもしれない」という考えにとらわれがちです。
認知行動療法では、こうした思考のクセを修正し、「現実的な捉え方」を学ぶことを目指します。
● 「責任の重さ」を見直す
✔「本当に自分が100%責任を負わなければならないのか?」
✔「他の人は同じ状況でどう考えるだろう?」
✔「過去に問題が起こったことはどれくらいあるのか?」
● 「最悪のシナリオ」を現実的に検討する
✔「手を洗わなかったら、家族が病気になる確率はどれくらいか?」
✔「鍵を閉め忘れたら、すぐに泥棒が入るのか?」
✔「仮に最悪の事態が起きたとしても、自分で対処できるのでは?」
こうした現実的な視点を持つことで、「不安=即行動しなければならない」という思考パターンを変えていきます。
2-2. 行動の変容(強迫行動を減らす)
「強迫行動を減らす」ための代表的な方法として、「曝露反応妨害法(ERP)」が挙げられます。
● 曝露(Exposure)
あえて不安を感じる状況に身を置く
具体例
→「手洗いをすぐにせずに10分待つ」「鍵の確認回数を減らす」
● 反応妨害(Response Prevention)
不安を打ち消す行動(強迫行動)を控える
具体例
→「手洗いをしない」「鍵の確認を1回にする」
この方法を繰り返すことで、「不安があっても、時間が経てば自然に和らぐ」ということを体感し、徐々に強迫行動の頻度を減らしていきます。
2-3.強迫性障害治療におけるカウンセリングの役割
強迫性障害は一人で克服するのが難しい疾患ですが、適切な治療を受けることで、症状を改善することが可能です。
まずは…
①強迫性障害の認知パターンを理解し適切な修正を行う
②「不安をコントロールできる」という感覚を身につける
③カウンセラーと共に、強迫行動を減らしていくトレーニングを行う
一人で悩まず、まずは専門家に相談し、強迫性障害から解放されることを目指してくださいね。
参考論文
----------------------------------------------------------------------
こころのケア心理カウンセリングRoom
兵庫県芦屋市浜芦屋町1-27 サニーコート浜芦屋302号
電話番号 : 090-5978-1871
----------------------------------------------------------------------
この記事の執筆者
駒居 義基(こころのケア心理カウンセリングルーム 代表)
心理カウンセラー(公認心理師)。20年以上の臨床経験と心理療法の専門性を活用して、神戸市や芦屋市、西宮市の近隣都の方々にお住いの心のお悩みを抱えている方に対して、芦屋市を拠点に最適なサポートを提供しています。
プロフィールはこちら