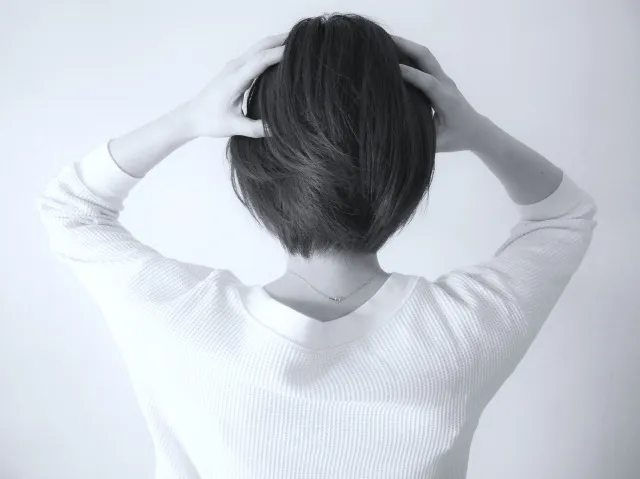双極性障害における生活への影響と対処法:認知機能の問題と感情調節の関係
2025/03/20
みなさん、こんにちは。
神戸市や芦屋市、西宮市などの近隣都市で活動しているこころのケア心理カウンセリングルームの心理カウンセラー(公認心理師) 駒居義基です。
さて、双極性障害と聞くと「気分の波が激しい」「躁とうつを繰り返す」といった症状を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、双極性障害には気分の変動だけでなく、認知機能(記憶力や注意力、判断力など)にも問題が生じることが研究で明らかになっています。
特に、認知機能の低下は感情調整に影響を及ぼし、症状の悪化や社会生活の困難さにつながることが指摘されています。
今回は、Lima et al.(2018)の研究を踏まえつつ、双極性障害における認知機能の問題と、それが感情調整にどう関係するのかを詳しく見ていきましょう。
1.双極性障害の認知機能障害とは?~「考える力」の問題が日常生活に与える影響~
双極性障害は、気分の波だけでなく、認知機能(ものを考え、記憶し、判断する力)にも影響を及ぼすことがあることが研究で明らかになっています。この「認知機能の障害」は、双極性障害のエピソード(躁やうつ)の最中だけでなく、症状が落ち着いている寛解期にも続くことがあるため、生活全般に影響を及ぼす重要な要素です。
1-1. そもそも「認知機能障害」とは?
認知機能とは、私たちが日常生活をスムーズに送るために必要な「考えるチカラ」のことです。
例えば、以下のようなことをスムーズに行うために必要な能力を指します。
✔記憶する(新しい情報を覚え、必要なときに思い出す)
✔集中する(一つのことに注意を向け続ける)
✔計画を立てる(今日やるべきことを考え、順序を決める)
✔判断する(選択肢を比較し、適切な決定をする)
✔行動を抑える(衝動的な行動を防ぎ、冷静に考えて行動する)
このような認知機能がうまく働かないと、日常生活や仕事、対人関係などに支障が出ることがあります。
1-2. 双極性障害における認知機能障害の特徴
双極性障害の方は、以下のような認知機能の問題を抱えやすい傾向があります。
① 記憶力の低下
✔言語記憶(話を聞いて覚える力)や視覚記憶(図や場所を覚える力)が低下しやすい。
✔会話の内容を忘れやすいため、人間関係に影響が出ることもある。
✔仕事で指示されたことをすぐに思い出せないため、ミスが増えやすい。
具体例
✔「さっき説明されたことをすぐに忘れてしまう」
✔「人の名前や約束したことを思い出せない」
✔「書類の内容を何度も確認しないと覚えられない」
② 注意力や集中力の問題
✔一つのことに集中し続けるのが難しい
✔会話の途中で意識がそれてしまう
✔仕事や勉強をしていても、気が散ってしまい効率が落ちる
具体例
✔「本を読んでいても内容が頭に入らない」
✔「会議中に話を聞いているつもりが、途中で意識が別のことに向いてしまう」
✔「仕事をしていても、SNSや他のことが気になってしまい、なかなか進まない」
③ 実行機能の障害(計画や判断の難しさ)
✔計画を立てるのが苦手になり、順序立てて考えるのが難しくなる
✔柔軟な思考がしづらく、一度決めたことを変更するのが大変
✔状況に応じた適切な判断をするのが難しく、ミスが増える
具体例
✔「仕事で優先順位をつけるのが苦手」
✔「予定を立てても、何から始めればいいかわからず手が止まる」
✔「急な変更に対応できず、混乱してしまう」
④ 反応抑制の困難さ(衝動的な行動を抑えるのが難しい)
✔感情が高ぶったときに冷静になるのが難しく、すぐに行動してしまう
✔衝動的にお金を使ったり、人に強い言葉をぶつけてしまうことがある
✔怒りや不安を抑えるのが難しく、ストレスをためやすい
具体例
✔「カッとなって、後から後悔するような発言をしてしまう」
✔「気分が高まっているときに、必要のないものを衝動買いしてしまう」
✔「イライラしてつい仕事を投げ出してしまう」
1-3. 双極性障害の認知機能障害は、うつや躁のエピソードがなくても続く
認知機能障害は、「躁状態のときや、うつ状態のときにだけ起こるもの」と思われがちですが、研究によると「寛解期(症状が落ち着いている状態)にも続くことが多い」ことが分かっています。
つまり、双極性障害の治療では、気分の波を抑えるだけでなく、認知機能を改善することも大切なのです。
1-4. 認知機能の低下が日常生活に与える影響
双極性障害の認知機能障害があると、以下のような場面で困難を感じることが増えます。
● 仕事や勉強
✔指示を理解するのに時間がかかる
✔スケジュール管理が苦手で、締め切りを守るのが難しい
✔一つの作業に集中できず、ミスが増える
● 人間関係
✔相手の話を途中で忘れてしまい、誤解を招くことがある
✔感情のコントロールが難しく、衝動的に怒ってしまうことがある
✔計画を立てるのが苦手で、友人との約束を忘れてしまうことがある
● 日常生活
✔家の中を片付けるのが苦手で、すぐに散らかってしまう
✔お金の管理ができず、衝動買いをしてしまう
✔やるべきことを後回しにしてしまい、後で焦ることが多い
2. 認知機能と感情の関係~なぜ感情調整が難しくなるのか?~
双極性障害では、感情の起伏が激しいことが特徴的ですが、その背景には単なる気分の問題だけでなく、脳の中の認知機能(考える力)の低下が深く関係していることが知られています。
ここでは、認知機能の問題がどのように感情調整の難しさにつながるのかを詳しく解説していきます。
2-1.認知機能の低下が感情調整を難しくする理由
認知機能の中でも特に重要なのが、「実行機能」と呼ばれる能力です。
実行機能とは、計画を立てたり、物事を柔軟に考えたり、状況に応じた判断をするための認知機能です。
この実行機能が低下すると、感情を適切にコントロールすることが難しくなります。
例えば、通常ならストレスがかかったときでも…
✔「まずは落ち着いて状況を整理しよう」
✔「今すぐ対応が必要なのか、それとも後で考えても大丈夫なのか」
…というふうに、冷静に考えることができます。
しかし、実行機能が低下すると、こうした冷静な対応が難しくなり、目の前のストレスに対してすぐにパニックになったり、イライラしたり、衝動的に反応してしまいます。
その結果…
✔些細なことに対して怒りを爆発させてしまう
✔うまくいかないと感じるとすぐに落ち込んでしまう
✔自分をコントロールできない不安に陥る
…などのお辛い気分の変動が生じやすくなります。
具体例としては…
✔職場で少し厳しいフィードバックを受けたとき、冷静に受け止めて改善策を考えることができず、「もう自分には無理だ」とすぐに諦めてしまう。
✔家庭で小さな口論があった際に、冷静な対話ではなく感情的に相手を責めてしまい、後で大きな問題に発展する。
このように、実行機能の低下によって感情の安定性が大きく崩れてしまうのです。
2-2.ネガティブな情報の処理が強くなることの影響
双極性障害を持つ人の特徴として、「ポジティブな情報よりもネガティブな情報を強く記憶してしまう」という認知的な傾向があります。
一般的には、良い出来事や褒められたことなどのポジティブな情報は自己肯定感を高め、安定した感情を維持するのに役立ちます。
しかし、双極性障害の場合は…
✔ちょっとした失敗や批判的なコメントが、何度も頭の中で繰り返される。
✔良かったことや成功体験よりも、ネガティブな経験のほうが強く記憶されてしまう。
その結果、「自分はダメだ」「また失敗するに違いない」といった否定的な考えが増え、自己評価が下がってしまいます。
具体例としては…
✔仕事で10個中9個成功しても、1個のミスだけを繰り返し思い出し、「また失敗したらどうしよう」と不安が増してしまう。
✔家族や友人からポジティブなコメントをもらっても、1つだけ指摘されたことばかりが気になって落ち込んでしまう。
こうしたネガティブな情報処理が強まることで、不安や抑うつなどのネガティブな感情が強化され、感情のコントロールがさらに難しくなります。
2-3.衝動的な行動を抑えるのが難しくなる
さらに、双極性障害では感情が強くなったときに、それを一旦止めて落ち着いて考える力(反応抑制)が低下し、衝動的な行動が増えることが分かっています。
これは、強い感情が湧き上がった瞬間に、「ちょっと待って、冷静になろう」というストッパーが効かなくなる状態を指します。
具体的には…
✔怒りが湧いたとき、相手を怒鳴ったり、攻撃的な発言をしてしまう。
✔不安が強くなると、それを解消するために衝動的に買い物をしてしまったり、暴飲暴食してしまう。
…といった行動が増えます。
日常生活では、例えば以下のような場面があります
✔友人や家族と些細なことで口論になった際、本来なら冷静に話し合いで解決できるところを感情的になり過ぎてしまい、大きなトラブルに発展する。
✔「ストレスが溜まった」と感じた瞬間に、高額な商品を何も考えずに購入してしまい、後から経済的な問題を抱えてしまう。
こうした衝動性は人間関係や経済面、さらには健康面にまで影響を及ぼし、生活の質を大きく下げてしまう可能性があります。
2-4.まとめ:認知機能と感情調整の密接な関係を理解する
以上のように、双極性障害の人々が抱える認知機能の問題(実行機能、ネガティブ情報処理、反応抑制)は、感情調整を困難にし、日常生活のさまざまな面で問題を引き起こします。
しかし、これらの認知機能の問題は、自分の努力不足や性格の問題ではありません。
脳の情報処理の仕方が影響しているため、意識的なトレーニングや専門的なカウンセリング、治療を受けることで改善可能なものです。
3. 認知機能の改善による感情調整の向上
認知機能が低下していると、感情の波をうまくコントロールできず、生活にさまざまな支障が出てしまいます。
しかし、適切なトレーニングやサポートを受けることで、認知機能を改善し、感情調整の力を高めることが可能です。
3-1.認知機能を鍛えるトレーニング
✔記憶トレーニング:日記をつける、覚えたことを声に出して復習する
✔注意力強化:マインドフルネス瞑想、集中して読書をする
✔計画力を鍛える:TODOリストを活用し、優先順位をつける
✔反応抑制のトレーニング:一呼吸おいてから行動する習慣をつける
3-2.認知行動療法(CBT)の活用
認知行動療法(CBT)は、「自分の考え方のクセを見直し、より柔軟な思考を身につける」 ための心理療法です。
特に、双極性障害の方が持ちやすい「ネガティブな思考の強化」を防ぐために役立ちます。
4. まとめ
双極性障害における認知機能の低下は、感情調整の困難さと深く関係しており、症状の悪化や社会生活の困難につながる可能性があります。
しかし、適切なトレーニングやカウンセリングを活用することで、認知機能を改善し、より安定した生活を送ることが可能です。
「自分の認知機能や感情のコントロールに不安がある」という方は、ぜひ専門家のサポートを受けながら、一歩ずつ前進していきましょう。
参考論文
Cognitive deficits in bipolar disorders: Implications for emotion
----------------------------------------------------------------------
こころのケア心理カウンセリングRoom
兵庫県芦屋市浜芦屋町1-27 サニーコート浜芦屋302号
電話番号 : 090-5978-1871
----------------------------------------------------------------------
この記事の執筆者
駒居 義基(こころのケア心理カウンセリングルーム 代表)
心理カウンセラー(公認心理師)。20年以上の臨床経験と心理療法の専門性を活用して、神戸市や芦屋市、西宮市の近隣都の方々にお住いの心のお悩みを抱えている方に対して、芦屋市を拠点に最適なサポートを提供しています。
プロフィールはこちら