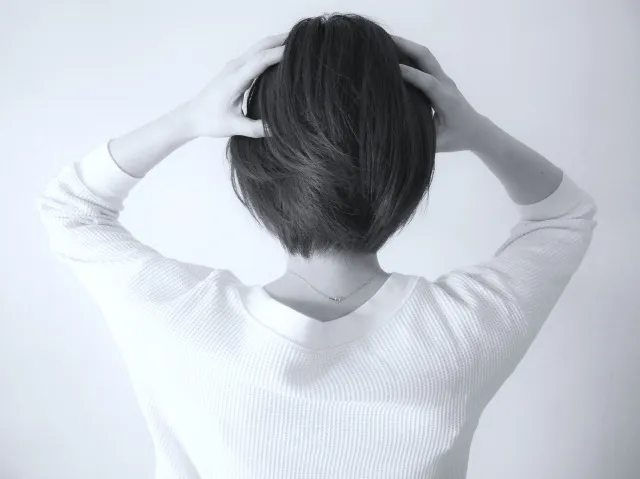その自信、ホンモノですか?「自分を苦しめる自尊心」について
2025/03/28
みなさん、こんにちは。
神戸市や芦屋市、西宮市などの近隣都市で活動しているこころのケア心理カウンセリングルームの心理カウンセラー(公認心理師) 駒居義基です。
「もっと自信を持ちたい」「自尊感情を高めたい」と願う方は多いですが、実は自尊感情が高ければいいというわけでもありません。
実際に、表面的には自信満々に見えても、他者評価に振り回されて疲れてしまう方は珍しくありません。
そこに関わる大切な概念が「随伴性自尊感情」。
そこで今回は、その落とし穴と、外的要因に左右されない「本物の自尊感情」のポイントを解説します。
1. 外的評価に縛られた自尊感情とは?
自分の存在価値を感じるために、他者がくれる評価や褒め言葉を必要とすることは珍しいことではありません。
しかし、このように「他人が何と言うか」に強く依存して自分の価値を決めるのは、じつは不安定な自尊感情の表れです。
ここでは、こうした自尊感情の仕組みと、それがどのように私たちの心を不安定にさせるかを詳しく解説します。
1-1.他人の目が気になりすぎる「随伴性自尊感情」
● 随伴性自尊感情とは
「随伴性」とは「何かにくっついている(依存している)」という意味です。
随伴性自尊感情は、外見・成績・SNSでの反応・他者からの称賛など、「外的な要素」と自尊感情がセットになっている状態を指します。
たとえば、「友達から褒められると自分に価値がある気がするけれど、誰も褒めてくれないと自信がなくなる」という場合、他者の評価がなくては自分を肯定しにくいわけです。
● 具体的な例
✔「SNSのいいねが多いときはとても気分がいいが、少ないと落ち込む」
✔「褒められないと(あるいは成績が下がると)『自分には何もない』と感じてしまう」
こうしたパターンが続くと、いつも周囲のリアクション次第で自分の気分が大きく上下し、「自分の軸」をもつことが難しくなってしまうのです。
1-2.なぜ不安定なのか
● 評価が得られないと一気に落ち込む
周りから良い評価を得られなかったり、少しでも批判される出来事があると、自分の根本的な価値が否定されたように感じやすくなります。
結果として、「自分はダメだ…」と強く思い込んでしまい、気分が大きく落ち込む原因になってしまいます。
● 長期的には心が揺れ続ける
たとえば、SNSで「いいね」が多い日は気分が高揚しますが、少なければ落ち込む…。
仕事で褒められれば自信が高まりますが、少し失敗を指摘されるだけで自分を責めてしまう…。
このように、外部要因で気分が上下し続ける状態では、安定した自尊感情を育むことが難しく、慢性的に不安がつきまといやすくなります。
● 「自信が高いはずなのに満たされない」悪循環
一見すると、自分に自信があるように映る人でも、実際には「評価がないと安心できない」という不安定さを抱えていることがあります。
褒められれば高揚感は得られますが、それは長続きしにくい「借り物の自信」とも言え、再び評価が途切れると不満や落ち込みに陥りがちです。
1-3.まとめ
随伴性自尊感情は、「他者の評価」など外的な条件に大きく依存しているため、評価が得られない瞬間に一気に不安が募り、自分自身に価値がないかのように感じてしまうという特徴があります。
もし、「誰かに認められないと安心できない」「少しの批判でズタボロになる」と感じたら、自分の自尊感情が随伴性になっていないか振り返ってみるのが大切です。
自分の価値を外部任せにせず、内側から「私はこれで大丈夫」と思える感覚を育てることが、本当の意味で“揺るぎない自尊感情”を築く第一歩になります。
2.健康的な自尊感情はどんな状態?
自尊感情をより安定した形で保つためには、他人の評価や比較に左右されず、自分自身を肯定できる感覚が大切です。
ここでは「自分なりの基準」をしっかりと持ち、内面から「これでいい」と思える自尊感情のあり方を解説します。
2-1.比較や評価に依存しない「自分なりの良し」
● 外部評価ではなく、内発的なモチベーションを重視する
たとえば「自分の才能や成果が周囲にどう評価されるか」ではなく、「自分が本当に楽しいと思えること」や「自分が大切だと感じる目標」にフォーカスしてみましょう。
周りの反応に振り回されずに、自分の意志や興味を優先できる感覚を育むことが、安定した自尊感情の基盤になります。
● 「自分らしさ」を軸にする
他人と比べて「優劣」を判断するのではなく、自分がもともと持っている性格や特性を認め、「これが自分らしさだ」と納得できると、他者との比較で落ち込む必要がなくなります。
たとえば、社交的ではない性格を「自分に合わない」と否定するのではなく、「少人数で深く関わるほうが向いている」ととらえるなど、自分に合った価値観を見つめ直すのも重要です。
2-2.自分の存在そのものを肯定する感覚
● 自分自身の存在をまるごと認める
他人の目や外見、評価などとは切り離して、「このままでも大丈夫」と思える感覚を育てると、ちょっとした失敗や批判を受けても、根本的な自己評価が揺らぎにくくなります。
たとえば、「少しミスをしてしまったが、それでも自分は十分頑張っている」と自分で自分に声をかけられる状態が理想的です。
● 生まれ持った価値を見直す
人は誰でも、生きているだけで何らかの価値を持っています。
周囲の意見に振り回されず、「自分には生きる意味がある」「自分なりのやり方で成長していける」と信じられるようになると、外部からの評価に一喜一憂しなくても自尊感情を保ちやすくなります。
2-3.まとめ
健康的な自尊感情とは、他人の評価や比較に頼らず、「自分という存在そのものが大切である」と思える状態を指します。
これが確立されていると、失敗や批判に直面しても、根本的な自信が損なわれにくくなります。
たとえ周囲からの評価が思わしくないと感じても、「自分はこれでいい」「自分には生きる価値がある」と思える軸を持つことで、日々の生活をより安定した気持ちで送れるようになるでしょう。
3.外的評価から離れるためのヒント
他人の目を気にしてばかりいると、ちょっとしたことで心が揺れ動き、自分の軸を失いやすくなります。
そこで、周囲の評価ばかりに振り回されず、自分の内面からくる自信を育むための2つのステップを詳しく解説します。
1) 自分の基準を見直す
● どんな基準で自分を評価しているかを整理する
まずは、いつも自分をどのように判断・評価しているかを書き出してみてください。
たとえば「外見が整っていないと自信がない」「SNSの反応が少ないと不安になる」など。
これにより、何を「自尊感情の土台」としているのかが明確になります。
● 外見や周囲の反応に頼りすぎるなら基準を変えてみる
もし「他人のほめ言葉」や「評価」にこだわりすぎていると感じたら、より内面に根ざした基準に置き換えることを検討しましょう。
たとえば、「人と比較して上手に話せるか」ではなく「その日の会話で何か前向きなことを言えたか」「自分なりに相手をサポートできたか」など、自分だけの達成感や意味を見いだせる基準を探ってみると、自尊感情が外的要因に左右されにくくなります。
2) 小さな成功体験を積む
● いきなり外部評価から離れようとしなくてOK
「他人の目を気にしない!」と意気込んでも、急にはうまくいかないことが多いものです。
そこで、まずは小さなステップから始めるのがポイントです。
● 好きなことや得意なことを活かして成功体験を重ねる
たとえば、好きな料理に挑戦してみたり、少しだけ得意なスポーツに取り組んだり、興味のある勉強を少しだけ進めたりしてみましょう。
ここで大事なのは、「周囲からどう思われるか」ではなく、自分が少し成長したり、できることが増えたりする感覚を味わうことです。
● 自分の中で「良し!」と言える瞬間を意識する
他人に認められなくても、「今日は昨日よりできるようになった」「この課題を期限通り終わらせられた」といった「自分のなかの合格ライン」を達成してみましょう。
これを何度か積み重ねると、外部の反応に頼らずとも、「自分はこれができるんだ」という実感が湧き、徐々に自信を培っていけます。
まとめ
自尊感情は、高ければ高いほど幸せになれるという単純なものではありません。
外見や周囲の評価に強く依存した「随伴性自尊感情」では、一見キラキラしていても、ちょっとした否定や批判で揺らいでしまうのが問題です。
本当に自分を肯定できる自尊感情は、外部の声に左右されず「自分らしさ」を根に持ったものです。
もし「自信がほしい」と感じるなら、外部評価から離れ、自分が何を大切にし、どんな行動を認めたいのかを見つめ直すところから始めてみましょう。
他人の評価を気にするクセを変えるのは簡単ではありませんが、「自分の基準を改めて見直す」→「小さな成功体験を積む」という手順を地道に行うことで、少しずつ外的要因から離れた自分らしい自尊感情を育めるようになります。
最初から完璧を目指すのではなく、まずは小さな一歩から。
外部の評価ばかりに振り回されず、「自分の良さ」に気づく習慣を身につけていきましょう。
----------------------------------------------------------------------
こころのケア心理カウンセリングRoom
兵庫県芦屋市浜芦屋町1-27 サニーコート浜芦屋302号
電話番号 : 090-5978-1871
----------------------------------------------------------------------
この記事の執筆者
駒居 義基(こころのケア心理カウンセリングルーム 代表)
心理カウンセラー(公認心理師)。20年以上の臨床経験と心理療法の専門性を活用して、神戸市や芦屋市、西宮市の近隣都の方々にお住いの心のお悩みを抱えている方に対して、芦屋市を拠点に最適なサポートを提供しています。
プロフィールはこちら