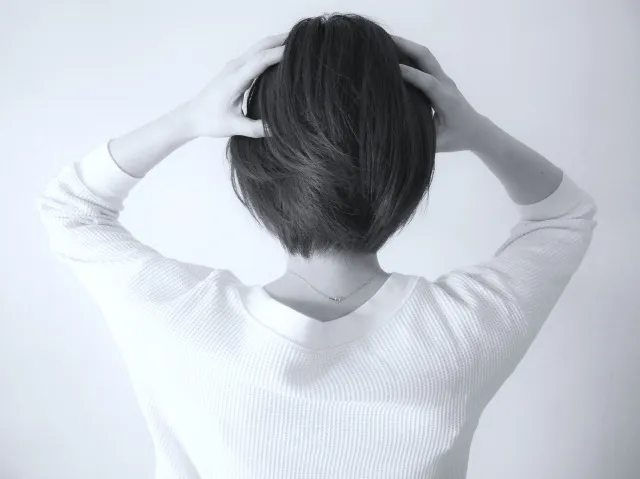アダルトチルドレンが感じる生きづらさとは?
2025/03/31
みなさん、こんにちは。
神戸市や芦屋市、西宮市などの近隣都市で活動しているこころのケア心理カウンセリングルームの心理カウンセラー(公認心理師) 駒居義基です。
幼少期の家庭環境が、人が大人になってからの人間関係や自己認識に深く影響するという傾向が生じることは、多くの方がご存じかと存じます。
たとえば、両親が情緒不安定だったり、家族同士の会話が少なかったり、あるいは何らかの依存症や精神的な問題を抱えていたりすると、子どもは十分な安心感や自己肯定感を得られないまま成長してしまうことがあります。
こうした背景を持つ人は、大人になってからも「自分はどうしたらいいのか」と迷いや生きづらさを感じやすい傾向があるのです。
これが、いわゆる「アダルトチルドレン」です。
そこで、このブログでは家庭環境の影響によって大人になっても苦しさを抱えやすい「アダルトチルドレン」という概念と、その背景・特徴について詳しく解説します。
また、実際にどのようなパーソナリティのパターンがあり、どんな対処やサポートが有効なのかにも触れていきます。
1. アダルトチルドレンとは?
1-1.アダルトチルドレンの概念と歴史的背景
アダルトチルドレン(Adult Child)という言葉は、もともとアルコール依存症の親のもとで育った子どもたちが大人になっても抱える心の傷や苦しみを指していました。
しかし、近年では、親が必ずしもアルコール依存症である必要はなく、家庭環境が機能不全(家族同士が適切なコミュニケーションや愛情を交換できない状態)であれば、同様の問題を抱える可能性があると考えられるようになっています。
1-2.幼少期の家庭環境が大人になった今も影響を及ぼす
機能不全家庭のもとで育った場合、たとえば親の暴言や育児放棄(ネグレクト)、家庭内の激しい口論などが当たり前になっていると、子どもは…
「自分は守られていない」
「安定した愛情を受けられない」
…と感じることが多くなります。
すると、自我を健全に育む機会が減り、以下のような困難を大人になっても抱えやすくなるのです。
感情面の不安定
→本来なら幼少期に身につけるはずだった安心感や自己肯定感が不足し、些細なことで不安や罪悪感を抱きやすくなる。
人間関係の生きづらさ
→相手の機嫌を伺いすぎたり、自分の気持ちを素直に表現できなかったりするなど、コミュニケーションで苦労しがち。
1-3.原因は多様
冒頭に述べたように、アダルトチルドレンはかつては「アルコール依存症の親を持つ子ども」というイメージが強い言葉でした。
しかし、実際には家族構成や親の問題の種類にかかわらず、子どもの頃に温かな愛情や安心が得られなかったり、過度な緊張状態が常に続くような家庭で育つことで、生きづらさを抱えた大人へと成長してしまう可能性があると言えます。
たとえば、家庭内の会話が極端に少ない、親が常にイライラしていて子どもの話を聞いてもらえない、あるいは家族の誰もが自分のことで手いっぱいで子どもの存在を後回しにしてしまう…。
そうした不適切な状況が日常的に続くと、子どもは「自分には価値がないのかも」「何をしても怒られるかもしれない」といった思い込みを形成し、結果として自己否定感や強い不安を持ちやすくなってしまいます。
2. アダルトチルドレンに見られる特徴
アダルトチルドレンとして育った方々の多くは、幼少期に体験した不安定な状況をなんとか乗り越えるために、独自の対処法や思考パターンを身につけました。
しかし、その方法が大人になってからも変わらずに続いてしまうと、現在の生活や人間関係に様々な困難をもたらすことがあります。
以下に挙げるのは、アダルトチルドレンの方に特にみられやすい特徴です。
(1) 自分を責めやすい・自己否定感が強い
● ちょっとした失敗でも「自分が悪い」と思い込む
周囲からすれば「それは誰にでもあるミスだよ」と言われるような出来事でも、アダルトチルドレンの方は過度に落ち込み、「やっぱり自分はダメだ」「また失敗した」と強い自己批判に陥りやすい傾向があります。
● 肯定的な言葉が耳に入りにくい
自分を責めるクセが染みついていると、「そんなことないよ」「大丈夫だよ」という周囲の言葉を素直に受け取れないことにもつながります。
「自分なんて…」と考えを深めてしまい、ポジティブなメッセージを拒否するような反応を取ってしまいがちです。
(2) 他人に依存しやすい、または誰も頼れない
● 「過剰な依存」と「完全な孤立」の両極端
幼少期に安定したサポートを得られなかった結果、必要以上に他人に頼らないと不安で仕方ないという人もいれば、「どうせ助けてもらえない」と考えて全く助けを求められない人もいます。
● 信頼関係の築き方がわからない
親子関係や家族関係が機能不全だったために、本来は子ども時代に学ぶはずだった「適切な距離感」や「互いに助け合うコミュニケーション」を習得できないまま大人になる場合があります。
その結果、相手に依存しすぎたり、逆に誰にも頼れず一人で抱え込んでしまったりするのです。
(3) 感情が不安定で衝動的になることがある
● 突然怒りが爆発したり、深く落ち込んでしまう
幼少期から常に緊張状態にさらされていたり、感情を抑え込んできた経験があると、自分の感情をコントロールするのが難しくなります。
些細なきっかけで怒りや悲しみが一気に噴き出し、自分でも制御できないほど衝動的な行動を取ってしまうことがあります。
● 「感情を感じる」こと自体に慣れていない
家庭環境が不安定だった子どもは、「感情を素直に表現すると危険(怒られる、無視される)」という学習をしているため、感情を上手に処理できず急に爆発させてしまうケースも少なくありません。
(4) 他者からの批判に異常に敏感
● 「自分が責められている」と感じるセンサーが過敏
幼少期に否定的な言葉を浴びせられていたり、親の機嫌をうかがい続けていたりした経験があると、「また怒られるのでは?」「自分が悪いと言われるのでは?」という警戒感が強まります。
そのため、少しの指摘や冗談にも過剰反応してしまうことがあります。
● 自分か周囲を責めるかの二択になりやすい
他者の一言が「批判」だと感じると、とっさに「私が全部悪い」「あなたこそが悪い」と極端な方向へ思考が偏りがちになってしまいます。
このような思考パターンが原因で、より深いコミュニケーションや問題解決がうまくいかない場合もあります。
3.アダルトチルドレンが抱える「生きづらさ」の背景
アダルトチルドレン(AC)の多くは、幼少期に安定感を得られない家庭環境を経験した結果、大人になっても「生きづらさ」や「慢性的な緊張感」を抱えています。
その背景には、トラウマ的体験や不安定な愛着形成が深く影響していると考えられます。
以下では、その理由をより具体的に説明します。
3-1.幼少期のトラウマとストレス反応
● 「いつ家が荒れるかわからない」という不安定さ
機能不全な家庭では、親が感情的になったり、家族同士の衝突が頻繁に起きたり、家の雰囲気が常にピリピリしていることが多くみられます。
そうなると子どもは「次はいつ怒られるか」「どんな機嫌で親が帰ってくるのか」という恐怖や緊張を常に感じながら過ごすことになります。
● 「サバイバルモード」が抜けない
こうした環境下で育つと、子どもは自分を守るために、「周囲の雰囲気や親の表情を鋭く読み取る」「失敗や衝突を避けるために常に神経を張り詰める」などの対処法を身につけます。
ところが、大人になって環境が変わっても、この緊張状態が続きやすく、ちょっとした物音や相手の表情の変化に敏感になって疲れてしまうのです。
● 慢性的な疲労感と警戒心
常に状況を察知する「サバイバルモード」によって、心と体は余分なエネルギーを消費し続けます。
そのため、普通の人がリラックスできる場面でも「油断すると危ないのでは」と無意識に構えてしまい、結果として疲れやストレスが抜けにくい状態に陥ります。
3-2.親との愛着形成の不安定さ
● 親が手いっぱいで子どもに十分なケアが行き渡らない
機能不全家庭の親は、自分自身の問題(精神的ストレス、家庭外のトラブルなど)に追われていて、子どもの感情や欲求にじっくり向き合えないことがあります。
子どもは本来ならば「安全基地」となるはずの親に安心して頼れず、心の支えを感じられません。
● 「自分は愛されないのでは…」という思い込みの形成
愛着を得られない子どもは、「自分が親に構ってもらえないのは、価値がないからだ」「一生懸命訴えても通じないんだ」と感じるようになります。
これが繰り返されることで、自己肯定感が育たず、他者との関係においても「どうせ私なんか」と自分を低く見てしまう思考パターンが定着しがちです。
● 対人恐怖・対人不安への影響
愛着形成が不十分だと、人との付き合い方もわからないまま成長することになります。
結果として、大人になってからも「他人をどう信じたらいいのか」「どこまで頼っていいのか」がわからず、過度に緊張したり、相手を遠ざけたりする傾向が出やすくなります。
4.パーソナリティサブタイプ:5つの分類
研究の中には、アダルトチルドレンを5つのパーソナリティサブタイプに分けて理解するアプローチもあります。
自分がどのタイプに近いかを認識することで、より具体的な対処法やセルフケアを考えやすくなります。
(1)Inhibited(抑制型)
特徴
→自己主張が苦手、引っ込み思案、常に自分が足りないと感じる、落ち込みや不安が強い
リスク
→対人関係を避けがちで、孤立したり思いを溜め込みすぎる可能性
ケアのポイント
→小さな成功体験やゆっくりしたセルフアファメーションを積み重ね、自分のペースで自己肯定感を育てる
(2)Externalizing(外向型)
特徴
→衝動的な行動や怒りの爆発、他者を責めがちな態度、物質依存に陥りやすい
リスク
→トラブルを起こしやすく、人間関係が不安定になりやすい
ケアのポイント
→衝動を感じたときの対処法(呼吸法・クールダウンタイムなど)を学び、自分と他人の境界線を認識する
(3)Emotionally Dysregulated(感情不安定型)
特徴
→感情が激しく揺れ動きやすい、自己イメージが安定しない、自己破壊的な行為に走ることがある
リスク
→気分の浮き沈みが大きく、うつ状態や境界性パーソナリティ障害につながるケースも
ケアのポイント
→感情の記録をとり、カウンセリングやセラピーで感情調整のスキルを学ぶ。自己理解が進むほど落ち着きやすい
(4)Reactive/Somatizing(反応・身体化型)
特徴
→ストレスや批判に対して過剰に反応し、頭痛や腹痛など身体症状も出やすい
リスク
→他人をコントロールしようとしたり、自分を追い込んだりしがち
ケアのポイント
→身体と心のつながりを意識し、ヨガや呼吸法などリラクゼーションテクニックを取り入れ、ストレスを身体に溜め込まない工夫をする
(5)High-functioning(高機能型)
特徴
→外部から見ると優秀で社交的、エネルギッシュ。周囲への気遣いや共感力も高い
リスク
→内面では不安や孤独を抱えていても、周囲に「完璧な人」と見られるため助けを求めにくい
ケアのポイント
→自分の弱さや不安を隠しすぎずに話せる環境を作ることが大切。周囲の期待に答えすぎない範囲でセルフケアを行う
まとめ:過去を知り、自分をいたわることで未来を変える
アダルトチルドレンが感じる生きづらさは、幼少期の家庭環境からの影響が色濃く残っているケースが多くみられます。
しかし、そのことを知り、適切なサポートやセルフケアを行うことで、生きづらさを徐々に緩和し、自分らしく安定した人生を築く可能性は十分にあります。
5つのサブタイプや自分特有の特徴を理解し、セルフケアをしっかりと行っていきましょう。
また必要に応じてカウンセラーを頼るのも1つの方法です。
過去のトラウマは変えられなくても、「今の自分」をいたわることで、新しい未来を切り開く力はきっと見つかります。
焦らず一歩ずつ、自分のペースで心の回復を目指していきましょう。
参考論文
Personality Subtypes in Adolescent and Adult Children of Alcoholics: A two part study
----------------------------------------------------------------------
こころのケア心理カウンセリングRoom
兵庫県芦屋市浜芦屋町1-27 サニーコート浜芦屋302号
電話番号 : 090-5978-1871
----------------------------------------------------------------------
この記事の執筆者
駒居 義基(こころのケア心理カウンセリングルーム 代表)
心理カウンセラー(公認心理師)。20年以上の臨床経験と心理療法の専門性を活用して、神戸市や芦屋市、西宮市の近隣都の方々にお住いの心のお悩みを抱えている方に対して、芦屋市を拠点に最適なサポートを提供しています。
プロフィールはこちら