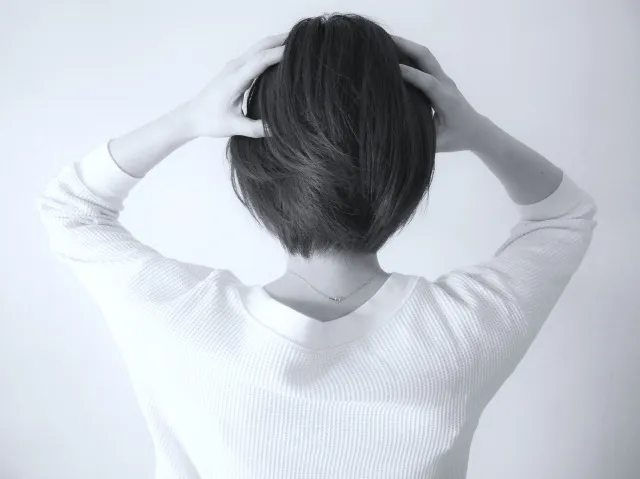ゼロにはできないストレス…だからこそ知っておきたいコントロールのヒント
2025/04/01
みなさん、こんにちは。
神戸市や芦屋市、西宮市などの近隣都市で活動しているこころのケア心理カウンセリングルームの心理カウンセラー(公認心理師) 駒居義基です。
さてストレスは多くの方にとって「諸悪の根源」のように思われがちです。
しかし、実はストレスにもプラスの側面があり、上手に活かすことで集中力を高めたり、仕事や日常生活のパフォーマンスをアップさせることも可能です。
そこでこのブログでは、ストレスの機能や影響を改めて見直しつつ、無理なく取り入れられるストレス管理法をご紹介します。
1. まずは知っておきたいストレスの正体」
1-1.そもそもストレスとは?
ストレスという言葉は「外部から圧力(刺激)が加わって歪みや緊張を引き起こした状態」を示します。
本来は物理学用語でしたが、そこから転用され、心身に加わる外的刺激と、その刺激によって生じる緊張状態を指すようになりました。
● 負の要因だけでなく、喜ばしい変化もストレスに
一般的には「悪天候」「寝不足」「多忙」「人間関係のトラブル」といったマイナス面だけがストレス源と想像しがちですが、じつは「結婚」「出産」「就職」などの新しいステージも、体や心に変化をもたらすためストレスの一種と捉えられます。
つまり、ストレス=ネガティブという先入観だけでは捉えきれない幅広い概念なのです。
1-2.「ストレス=悪」ではない?
● 適度な緊張感はパフォーマンスを上げる
たとえば、「締め切り前に集中力が高まる」「試験直前の追い込みで成果が出る」といった現象は、ストレスによる適度な緊張感がいい方向に作用している事例です。
逆に、まったくストレスがない状態だと、気が抜けてモチベーションが湧かず、行動が起こりにくくなることがあります。
● 大切なのはコントロール
もちろんストレスのかけすぎは心身に大きなダメージを与えますが、「まったく排除する」のではなく、自分が最適に動けるレベルに調整することが重要です。
ストレスがゼロの状態を目指すよりも、ストレスを自分の味方につけられるように管理・コントロールする姿勢が、健康的なストレスマネジメントにつながります。
2. ストレスの特性を知る~感じ方は人それぞれ~
ストレスと言うと、仕事の忙しさや生活環境の変化を思い浮かべる方も多いかもしれません。
しかし、たとえば人間関係の悩みや、一見小さなことに思える騒音・においなども、人によっては大きなストレスとなるものです。
ここでは、「ストレスの感じ方は人それぞれである」という2つのポイントを、具体的に見ていきましょう。
2-1.「自分が平気だから他人も平気」とは限らない
● 日常の小さな刺激が「大きなストレス」になることも
たとえば、ある食品の「独特な香り」を楽しむ人がいる一方で、その香りを強烈に不快と感じる人もいます。
これと同じように、ある人にとってはまったく気にならない音量の音楽や雑談が、別の人にとっては心を乱す大きな騒音になり得ます。
● 人間関係でもズレが生じやすい
「自分はこの程度の注意なら気にならない」というコミュニケーションでも、相手には「攻撃的」や「冷たい」と受け止められるかもしれません。
職場などで無理解な発言をされる方の多くは、こうしたストレスのメカニズムをご存じではありません。
あるいは同じジョークでも、自分は平気なのに相手は侮辱と感じるケースもありますよね。
これらはすべて、「ストレスの閾値(感度)が人によって違う」ことの表れです。
2-2.自分のストレスは自分が一番よく知っている
● ストレス源や強度は個人差が大きい
天候・気圧、におい、音、人間関係など、どんな状況でストレスを感じるかは人それぞれです。
たとえば、気圧の変化に弱い方は低気圧が近づくと頭痛や倦怠感が現れる場合が多くおられます。
また、人間関係のトラブルに強い方もいれば、わずかな衝突でも大きく落ち込んでしまう方もいます。
● 対策は「自分に合った形」で立てる
自分の苦手を知っていれば、あらかじめ対処策を用意できます。
たとえば…
気圧敏感
→天気アプリで気圧変化をチェックし、体調管理を工夫する
騒音が苦手
→集中が必要なときは静かなカフェや図書館を利用したり、イヤホンを活用する
人間関係のストレス
→合わないタイプの人とは必要最低限のやり取りにとどめる、もしくは上手に距離を取りながら協力を依頼できるようなシステムを考える
ストレス回避や軽減策を先回りして考えることで、急な刺激や不調に振り回されずに済みます。
2-3.「気づき」が自己管理の第一歩
どんなストレスがどのくらいの強度で自分に影響するのかは、ほかの誰よりも自分自身が一番よくわかるはずです。
とはいえ、普段意識していないと把握しきれない部分もあるでしょう。
そこで、「ストレス日記」をつけたり、身体の反応や感情の動きに注意を向けたりすることで、「自分だけのストレスマップ」を徐々に描いていくことができます。
そうした理解が深まるほど、効果的なストレス対策を組み立てやすくなるのです。
3. 自分のストレスを「見える化」する「ストレス日記」
3-1.なぜストレス日記が有効?
ストレスの仕組みを理解していても、「何がどのくらい自分を追い詰めているのか」を具体的に把握しなければ、対策を立てるのは難しいものです。
そこでおすすめなのが「ストレス日記」。
ストレスを感じたときや場面を記録していくことで、どんな状況でどの程度のストレスが頻発しているかを可視化できます。
3-2.記録項目(見本)
① 日時
ストレスを感じたタイミングを正確に記録。
例:「6月1日 14時ごろ」
② ストレス内容・状況
どんな出来事や状態でストレスが発生したのか、簡単に書き留めましょう。
例:「隣の席の雑談が気になって仕事に集中できなかった」「昔の失敗をふと思い出した」
③ 幸福度(0~10点)
ストレスを受けたあとの気分をざっくり数値化します。
例:「幸福度3/10(結構しんどい)」
④ 感情
「怒り」「悲しみ」「焦り」「不安」など、一言でもいいので具体的に感情を記述。
例:「イライラが止まらない」「思い出して悲しくなった」
⑤ 身体反応
頭痛、肩こり、動悸、体が熱くなるなど、身体面の変化を観察してメモ。
例:「頭が重くなり、心拍数が上がった」
⑥ どのように対処したか、そして効果はどうだったか
ストレスを感じた際に取った行動や対処法を記録し、それがどの程度役に立ったかも書きましょう。
例:「一旦席を離れて深呼吸した → 気分が少し落ち着いた」「まったく対策しなかった → ストレスが続いた」
3-3.分析のポイント
● 頻発するストレスは何か?
記録を見返して、同じような出来事や環境でストレスを感じていないか確認します。
● 最も影響が大きいストレスは?
幸福度が低下しやすい状況を把握することで、自分にとってダメージの大きい要因が見えてきます。
● 危険なシチュエーションを想定する
「どんな場所・どんな人・どんなタイミングでストレスが高まるのか」を知るだけでも、事前対策や心の準備が可能になります。
● 効果的な対処法は何か?
「外に出て散歩するとスッと楽になる」「誰かに話すと落ち着く」といった成功パターンを見つけ、今後も同じシーンで活かすようにしましょう。
まとめ
ストレス日記は、自分がどのような状況でストレスを感じ、そのときにどんな行動を取り、結果がどうだったか、というものを客観的に振り返るためのツールです。
いったんデータとして蓄積すれば、頻発するストレス源や、自分に合った対処法も自然に見つかっていきます。
日々忙しい中、わざわざメモを取るのは面倒かもしれませんが、習慣にして続ければ続けるほど、ストレスマネジメントがぐっとしやすくなるでしょう。
さまざまな対処法を試しながら、記録を通して自分のストレスに気づき、コントロールしていきましょう。
----------------------------------------------------------------------
こころのケア心理カウンセリングRoom
兵庫県芦屋市浜芦屋町1-27 サニーコート浜芦屋302号
電話番号 : 090-5978-1871
----------------------------------------------------------------------
この記事の執筆者
駒居 義基(こころのケア心理カウンセリングルーム 代表)
心理カウンセラー(公認心理師)。20年以上の臨床経験と心理療法の専門性を活用して、神戸市や芦屋市、西宮市の近隣都の方々にお住いの心のお悩みを抱えている方に対して、芦屋市を拠点に最適なサポートを提供しています。
プロフィールはこちら