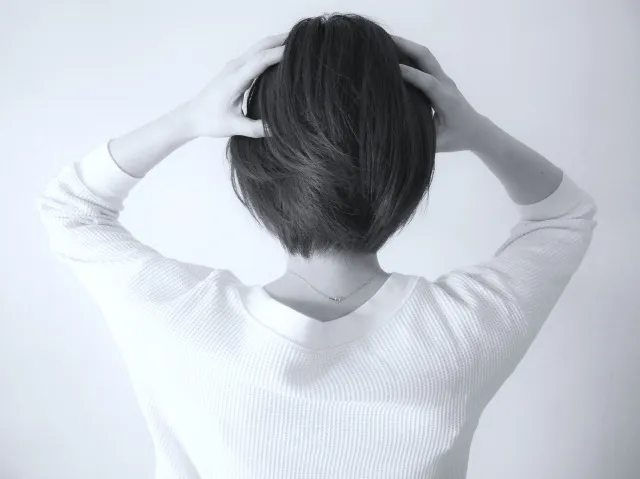ぐるぐる思考がうつ病や不安を強める理由とは?
2025/03/23
みなさん、こんにちは。
神戸市や芦屋市、西宮市などの近隣都市で活動しているこころのケア心理カウンセリングルームの心理カウンセラー(公認心理師) 駒居義基です。
さて、うつ病や不安が強くなると、どうしても同じ事、しかもネガティブな内容のことをぐるぐると考えてしまう…という状況が生じやすくなります。
この「ぐるぐる思考」は専門的には「反芻思考(はんすうしこう)」と呼ばれています。
この、同じ悩みや不安を何度も頭の中で繰り返してしまう「反芻思考」は、うつ病や不安を抱える方の気分を落ち込ませるだけでなく、心の健康に大きな影響を与えることが分かっています。
そこで今回は、研究から明らかになった反芻思考が抑うつ症状や不安症状に与える影響についてみていきたいと思います。
1. 反芻思考と抑うつ症状との関連性
最新の研究(Nolen-Hoeksema, 2000)では、反芻思考がうつ症状と非常に深く結びついていることが明らかになっています。
具体的には、反芻思考とは…
✔「どうして自分だけがこんなにつらいんだろう」
✔「私の人生はいつになったらよくなるんだろう」
✔「どうせ何をしてもうまくいかないだろう」
といった、自分の状況や気持ちを繰り返し繰り返し考えてしまう心の癖を指します。
こうした思考は、一見すると問題を解決するための努力のように見えますが、実際には問題を解決するどころか、気分をさらに落ち込ませる原因になってしまいます。
1-1.研究で明らかになった反芻思考の影響
Nolen-Hoeksema(2000)が行った研究によると、反芻思考を強く持っている人ほど、1年後に抑うつ症状が重くなる可能性が高いことが分かりました。
特に注目すべきなのは、調査の開始時点でまったくうつ症状がなかった人でも、反芻思考が強い場合、1年後に新たに抑うつ症状を発症するリスクが高まっていた点です。
つまり、反芻思考が強い人は、現時点で症状がなくても将来的なうつ病発症のリスクが高くなる可能性があるということです。
これは、反芻思考が「ネガティブな気分を維持し、強化してしまう」というメカニズムを持っているためです。
簡単に言うと、繰り返し否定的なことを考えるうちに、心が徐々に悲観的で落ち込みやすい状態になり、うつ症状が現れやすい「心の土壌」が作られてしまうのです。
1-2.抑うつ症状がすでにある人に対する影響とは?
では、すでにうつ病を抱えている方はどうでしょうか?
研究では、反芻思考だけでうつ病の慢性化リスクは判断できないという結果でした。
つまり、すでにうつ病を抱えている方の慢性化リスクは反芻思考だけではなく、その時点でのうつ症状の重症度」も考える必要があります。
しかし、だからといって反芻思考が問題でないわけではありません。
むしろ、反芻思考は症状の重症度を高めたり、治療や回復を妨げたりする重要な要因として働き続けます。
1-3.反芻思考がなぜうつ症状を引き起こすのか?
反芻思考がうつ症状を引き起こすメカニズムは、次のように説明できます。
✔反芻思考を繰り返すことで、ネガティブな感情が常に活性化される。
✔問題解決や気分転換といった前向きな行動がとりにくくなり、気分の改善が難しくなる。
✔自己否定的な考え方が強化され、自己評価が低下する。
✔周囲との交流を避けるようになり、社会的孤立が進む。
このように、反芻思考は「ネガティブな感情→ネガティブな思考→さらなる落ち込み」という悪循環を作り出してしまいます。
これが続けば続くほど、抑うつ症状は悪化し、回復が困難になるのです。
2.反芻思考が不安症状にも影響を与える理由
一般に反芻思考は「抑うつ症状」と密接な関連性があることがよく知られていますが、近年の心理学研究によって、不安症状にも非常に大きな影響を与えることが明らかになっています。
では、なぜ反芻思考が抑うつ症状だけでなく、不安症状まで強めてしまうのでしょうか?
2-1「未来への不確実性」に対する過度な意識
反芻思考を持つ方は、「この先どうなるかわからない」「本当に自分で状況をコントロールできるのか?」という、未来に対する不確実性や不安定さに注目してしまう傾向があります。
例えば、仕事や勉強、人間関係で何か問題が起きたとき、通常なら「きっと大丈夫」「そのときになったら考えよう」と考えることもできます。
しかし、反芻思考が強い方は、「失敗したらどうしよう」「ずっとこの状況が続いてしまうかもしれない」「自分ではもうどうにもならないかもしれない」といった思考にとらわれてしまうのです。
こうした未来への不確実性を繰り返し考えてしまうことで、まだ起こってもいない悪い状況をリアルに想像してしまい、心の中で常に警戒態勢を取るようになります。
この結果、緊張感や焦りが日常的に増え、慢性的な不安へとつながっていくのです。
2-2.不確実性への注意が不安を増幅させる悪循環
反芻思考が不安を強める最大の理由は、不安な感情や考えを繰り返し心の中で再生してしまうことにあります。
一度不安を感じ始めると、反芻思考の強い方はその不安な感情を頭の中で何度も繰り返し検討し、「なぜこんなに不安なんだろう」「どうしてこの状況になってしまったんだろう」「いつまでこの不安が続くんだろう」といった思考にとらわれます。
これが続くと、脳や身体が常に不安な状態を維持し続けるようになり、やがて「不安を感じる」こと自体が習慣化します。
つまり、不安が持続的に心の中に留まり、それを繰り返し考えることで、結果として不安そのものがどんどん増幅されてしまうという悪循環に陥ります。
具体的には、次のような状況が起こります。
①「明日のプレゼンはうまくいくかな?」と不安を感じる
②その後「もし失敗したらどうしよう」「周囲に迷惑をかけてしまったらどうしよう」と考え続ける
③心臓がドキドキし、不安がさらに強まる
④その不安がさらに別の不安を生み出す…というサイクルが形成される
2-3.コントロール感の欠如と自己効力感の低下
また、反芻思考は「自分で状況をコントロールできないかもしれない」という感覚を生み出します。
不安を感じる状況に対して繰り返し考え込むと、自分がその問題を解決したり対処したりする能力(自己効力感)が徐々に低下してしまいます。
自己効力感が低下すると、「自分にはこの状況を改善する力がない」と感じるようになり、さらなる不安や無力感を生みます。
そうすると、問題解決のための行動を取ることも難しくなり、不安感が持続してしまうという悪循環を作り出します。
具体例としては…
✔「人間関係のトラブルが解決できない」と繰り返し考えるうちに、「自分は人間関係を改善する力がない」と感じるようになり、友人や同僚と関わることを避けるようになる
✔「仕事でミスが多い」と考え込むうちに、「自分は仕事をコントロールできない」と感じてしまい、実際のパフォーマンスまで低下してしまう
このように、反芻思考が不安を強めるだけでなく、行動まで消極的にしてしまい、さらなる不安を生む原因になります。
3.抑うつ・不安混合状態への反芻思考の影響
近年の研究では、反芻思考が特に「抑うつ症状」と「不安症状」が混在する状態(抑うつ・不安混合状態)の方において、非常に強く現れることが明らかになっています。
抑うつ症状だけを持つ方や、不安症状だけを持つ方と比べて、両方を抱えている方は、反芻思考の程度が際立って高いことが確認されています。
その理由として、この状態では…
✔不確実性:未来がどうなるかわからない、自分で状況をコントロールできない
✔絶望感:(どうせ状況は良くならない)
…という二種類のネガティブな思考が交互に繰り返されるためです。
たとえば、不安症状が強いときには…
✔「本当にこの状況は大丈夫だろうか?」
✔「私はこの問題をコントロールできないのではないか?」
…という不確実な未来に対する不安が繰り返されます。
そして、これによりストレスや焦りが高まってしまいます。
一方で抑うつ症状が強まると…
✔「どうせこの状況は良くならない」
✔「自分には何もできない」
✔「もう何をやっても無駄だ」
…というような絶望的な気持ちや自己否定的な考えが強化されます。
このように、不確実な未来に対する不安と、絶望的な気持ちが交互に反芻されることによって、精神的なエネルギーがさらに消耗され、抑うつ症状と不安症状が相互に強まり、悪循環が形成されてしまうのです。
また、この悪循環は日常生活にも深刻な影響を及ぼします。
たとえば…
✔仕事や勉強に集中できなくなる。
✔人とのコミュニケーションが億劫になる。
✔「自分はダメだ」「状況が悪化するのではないか」といった思いが頭を離れず、日常生活の質が著しく低下する。
…という状況につながってしまいます。
4.反芻思考を軽減するための具体的な対策
反芻思考は自分の意思だけで止めるのが難しい場合も多いものです。
しかし、次のような具体的な方法が効果的です。
● マインドフルネスを取り入れる
「今この瞬間」に意識を集中させることで、不安や抑うつに対する反芻を断ち切りやすくなります。
● 考えを紙に書き出す
頭の中で繰り返される思考を紙に書き出すことで、思考の整理ができ、客観視が可能になります。
● 認知行動療法(CBT)を受ける
認知行動療法は、反芻思考の軽減に有効な心理療法です。
専門家のサポートを受けることで、自分の思考パターンを具体的に変えていくことができます。
まとめ
反芻思考がうつ病や不安症状に及ぼす影響はとても大きいですが、それはうつ病や不安を抱えている方自身の問題や性格のせいではありません。
反芻思考を少しずつ変えることで、抑うつ症状や不安症状が改善する可能性があります。
必要に応じて医療サービスやカウンセリングを活用しながら、反芻思考の悪循環から抜け出していきましょう。
参考論文
The Role of Rumination in Depressive Disorders and Mixed Anxiety/Depressive Symptoms
----------------------------------------------------------------------
こころのケア心理カウンセリングRoom
兵庫県芦屋市浜芦屋町1-27 サニーコート浜芦屋302号
電話番号 : 090-5978-1871
----------------------------------------------------------------------
この記事の執筆者
駒居 義基(こころのケア心理カウンセリングルーム 代表)
心理カウンセラー(公認心理師)。20年以上の臨床経験と心理療法の専門性を活用して、神戸市や芦屋市、西宮市の近隣都の方々にお住いの心のお悩みを抱えている方に対して、芦屋市を拠点に最適なサポートを提供しています。
プロフィールはこちら